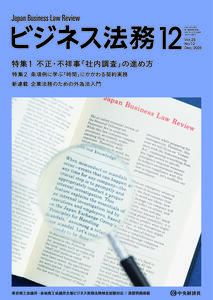
社内調査の全体像
竹内 朗
企業にとって不祥事は,「あってはならないもの」と遠ざけるのではなく,「必ず起きるもの」と正面から向き合い,その対応に万全を期して,不祥事による企業価値の毀損を最小限にとどめる方策を考える必要がある。そして,不祥事対応の出発点として実務上重要になるのが「社内調査」である。
調査の端緒
渡邉宙志
不祥事対応の要は,不祥事をいかに早期に発見できるかという「発見統制」の強化にある。3ラインモデルを意識した日常業務におけるレポートライン上の報告,内部通報や社内アンケートなどのレポートライン外の情報提供,さらには外部通報窓口や報道・SNS等による外部からの指摘まで,多様な調査の端緒を把握し,迅速かつ的確に対応できる体制を,平時から全社的に整備しておくことが不可欠である。
調査対象事実(調査スコープ)の設定
田中伸英
社内調査を行う場合,どこまで,何を調査するのかという調査範囲の設定がきわめて重要となる。必要十分な調査範囲の設定なくして,ステークホルダーからの信頼回復と企業価値の再生はありえない。では,どのように調査範囲を決定すればよいのか。必要十分な調査範囲の設定のためには,「横の拡がり」と「縦の拡がり」を意識する必要がある。本稿では「横の拡がり」と「縦の拡がり」を中心に調査範囲の設定方法について解説する。
調査体制の構築
徳山佳祐
最適な調査体制を構築するためには,調査チームに「独立性」と「専門性」を備えることが求められるが,これら2つの要素をどのような人材によって確保することができるかを悩む場面も少なくない。本稿では,最適な調査体制を構築するにあたって,独立性と専門性をどのように確保するか,調査体制をどのように選択するかについて,調査実務に適した有効な考え方や手法を探りたい。
調査環境の整備
福田恵太
不祥事の社内調査は,原因究明に必要十分な調査環境の整備が前提となる。調査チームには,資料・情報への自由なアクセス権,外部専門家を含む十分な予算,経営陣による関連部署への協力命令,調査の密行性確保等,自ら必要な調査環境を整える努力がまずは求められる。それにより,信頼性ある証拠に基づく正確な事実関係の把握,適切な原因究明,有効な再発防止策の構築が可能となる。
調査計画の策定と機関決定
池永朝昭
不祥事の調査は,発覚直後の初動調査を経て本格的な調査が開始される。その際に重要なのは調査計画の策定である。不祥事調査では,企業価値再生のため事実の解明,原因分析および再発防止が迅速に行われることが必要であるから,調査プロセスの管理が大事である。そのために,調査期限,調査対象事項,調査担当者および分担,調査手法,報告書作成期間等についてあらかじめ計画を策定すべきである。本稿ではそれらを解説する。
客観的証拠の保全・収集・検証
神田詠守
社内調査は,証拠を収集・検証して不祥事に関する事実を認定していく作業であるが,客観的証拠は,不祥事の痕跡が物自体に記録されたものであるため,供述証拠に比べて人為的な影響を受けにくく,調査においてきわめて重要な証拠となる。一方で,故意・過失を問わず,破棄・改ざん・消去されるリスクがあるため,その保全・収集には留意が必要となる。本稿では,客観的証拠の保全・収集・検証についての実務上の留意点を解説する。
関係者ヒアリング
田畑瑠巳
関係者へのヒアリングは,客観的証拠のみではわからない事実関係の隙間を埋める,新たな証拠を発見する,対象者の動機や心情等を明らかにする等の目的を有しており,事案の全容解明や,十分な原因究明,再発防止策の策定のため重要なプロセスとなる。もっとも,ヒアリングは,その手順や技法が適切でなければ,十分な結果は得られない。本稿では,関係者ヒアリングについての実務上の留意点を解説する。
調査報告書の作成
岩渕恵理
ここまで,調査体制や調査手法について説明してきたが,実際に行った調査の内容を「調査報告書」という形でまとめることは,経営陣が経営判断を行うために非常に重要なプロセスとなる。本稿では,その経営判断に資するような「調査報告書」の作成方法や,そのなかで特に重要な「事実認定」の手法について解説する。
調査終了後の対応
中島永祥
不祥事に関する調査報告書が提出され調査が終了すると,企業の経営陣は,調査結果に基づいて適切に事実分析および原因究明を行い,再発防止策を提示してステークホルダーからの信頼回復を図ることとなる。また,同時に関係者の処分や経営責任,法的責任を追及することも必要となる。本稿では,不祥事調査終了後の一連の対応について解説する。
伊藤和子
昨今,著名企業の人権対応が社会的批判にさらされる事案が相次いでいる。これは「ビジネスと人権」という発想が日本社会で浸透しつつある表れといえる。
森田 章
アメリカでは,1970年代初め,ダウ・ケミカル社の株主総会でナパーム弾を戦争目的のために製造および販売はしない旨の定款変更を求める株主提案がなされ,SEC(米国証券取引委員会)はこれを認めなかったが,連邦高裁はこれを認めた(拙著『現代企業の社会的責任』(商事法務研究会,1978))。これにより株主提案権が企業の社会的責任を追及する手段として,環境問題や人種差別問題についての提案事例が続いているようである。
川井信之
有価証券報告書の総会前開示の問題は,古くから議論があったが,昨年以降,大きな動きをみせている。
契約締結前・交渉中・締結後に意識すべきこと
田中かよ子
この特集では,「時間」にかかわる契約条件を掘り下げていくが,本稿では,まず,これらの「時間」にかかわる契約条件を含む契約の締結を行うにあたり,締結前・交渉中・締結後の全般を通して,いずれのタイミングで何を意識すべきかを検討する。
契約期間と更新条項の検討ポイント
官澤康平・荒牧孝洋
契約期間は,継続的契約の一般条項として定められることが多い規定である。また,同様に,契約期間終了時の更新条項についても,ひな形的に規定されることが多い。契約期間や更新条項の規定内容によっては,当事者間の認識の齟齬により思わぬトラブルにつながるケースもある。本稿では,契約期間や更新条項を規定する際の検討ポイントについて解説する。
契約終了・中途解約の勘所
金子順事
契約関係の終了は,取引の自然な一区切りであると同時に,当事者の利害が鋭く対立しやすい局面でもある。「時間」にかかわる契約実務については,終了の方法や手続,終了後の処理内容までを含めて,あらかじめ整理しておくことがとても重要である。本稿では,契約類型ごとの特徴と裁判例の示唆をふまえながら,終了条項を設計する際の留意点と,具体的な条文例を紹介する。
「完成」および「成果」にまつわる論点
――システム開発契約を題材に
澤田雄介
契約において「完成」は,請負契約とかかわる。そして,2020年4月施行の民法改正により,いわゆる「成果」完成型準委任に関する定めが新設された。契約に基づく仕事が「完成」したか(請負),「成果」が達成されたか(いわゆる成果完成型準委任),はいずれも契約に基づいて報酬請求を行うことができるかどうかを画する概念である。どのような要件を満たせば契約に基づく報酬請求ができるかについての紛争を防止するため,システム開発に関する契約を念頭において「完成」および「成果」にまつわる論点とそれに対応するための条項を検討する。
「期限の利益」と喪失
棚橋研斗
企業間取引から個人向けローンに至るまで,支払期日・契約の終了・更新等の「時間」にかかわる要素のなかで,「期限の利益」は,通常,債務者の資金繰りに猶予を与える一方,信用不安が生じた局面では債権者による債権回収のトリガーになる。条文の内容次第で期限の利益が喪失する事由および通知催告の要否等が左右されるため,実務上のリスクの観点から重要な条項といえる。本稿では,民法の規定を起点に,典型条項の書きぶりと包括的な条項についての裁判例の判断等を俯瞰し,実務上の留意点を概観する。
契約不適合責任の期間制限
伊藤敬之
購入した商品に不具合が見つかった場合に問題となる契約不適合責任。普段はあまり問題にならないが,いざというときに権利行使できるよう,契約不適合責任の期間制限について,あらためて整理を行う。
報酬の支払期限
――下請法・フリーランス法を中心に
高橋尚子・張 麗娜
企業間取引やフリーランスとの契約において,報酬の支払期限は日常的に直面する実務上の重要課題である。支払いが遅れれば,受注者にとっては資金繰りや生活基盤に直結する深刻な影響をもたらし,発注者にとっても法令違反や信頼失墜といったリスクを招く。こうした背景をふまえ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)と特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」という)が二本柱として整備され,取引の公正性と透明性を担保する役割を果たしている。
本稿では,両法における支払期限規制の概要を整理したうえで,実際の事例と契約実務における留意点を検討する。
文書・データの保存期間をめぐる対応
長野友法・鈴木直也
「保存してあるはずの契約書が見つからない」「いつの間にか議事録の添付資料が消えていた」――そんな文書管理の失敗は企業の信頼を揺るがしかねない。本稿では,文書等の「保存」に関する法制度を概観しつつ実務上の難点・勘所を解説し,文書等の保存管理に関する基本的な考え方の整理を行う。
海外取引における時間や期間の取扱い
野村 諭
国際取引の場合に,時間や期間の概念はどうかかわってくるか。日本国内取引・日本法契約と比べて,海外法準拠や海外当事者にどう対応するか,対応する領域が広がる海外法務の文脈では,優先順位をつけて対応していくことが求められるなかで,着目するポイントのなかに,時間に関する概念が登場してくる。
野呂悠登・林 里奈・梶原尚樹
EUデータ法は,データへの公平なアクセスおよびその利用に関するEU法であり,一部の規定を除き,2025年9月12日に適用が開始された。本稿では,EUデータ法について,概要と立法背景,具体的な規律,および実務対応を解説する。
2025年の主たる株主代表訴訟と制度趣旨再考
菱田昌義
2025年も残すところ2カ月となったが,本年も一定数の株主代表訴訟(会社法847条。以下「代表訴訟」ということがある)について,判決が言い渡され,あるいは新たな代表訴訟が提起された旨の報道がなされている。
代表訴訟は,2023年頃までと比して,①アクティビストによる積極的な代表訴訟提起,②第三者委員会による調査後の代表訴訟への発展など,従前はあまりみられなかった新たな局面を迎えようとしている印象を受ける。本稿では,代表訴訟の制度趣旨を再考し留意すべき視点を示すとともに,本年の代表訴訟からみえてきた課題について若干の説明を加えることで,現時点において,企業が認識しておくべき代表訴訟の現状について明らかにする。
ライフサイエンス・ヘルスケア分野のDD実務
――薬事規制および知的財産権の観点から(後編)
美馬拓也
前編では,ライフサイエンス・ヘルスケアM&Aの最新動向に触れたうえで,本分野における主要な関連法令の概要を示し,規制の根幹を成す薬機法を中心に概説した。あわせて,同法に基づく許認可制度を,医薬品,医療機器,医薬部外品および化粧品ごとに整理し,同制度がM&Aの買収ストラクチャーに与える留意点についても触れた。
後編では,ライフサイエンス・ヘルスケア分野におけるデューデリジェンス(以下「DD」という)の実務を前提に,まず知的財産に関する主要な検討ポイントを整理する。さらに,業種ごとの特性に応じた留意点について,実務経験をふまえて主要な論点を抽出し,各ビジネスにおけるDDの視点を紙幅の許す範囲で説明する。
遠藤元一
本書は,ガバナンスの根幹にかかわるテーマであり,会社法の中でも実務上の紛争が生じやすい「取締役の辞任と解任」に真正面から取り組み,辞任・解任に関する論点を網羅的に取り上げて探求した意欲作である。
PICK UP 法律実務書
『失敗しない「人と組織」――本質的に生まれ変わるための実践的方法』
高橋教嗣
社員のコンプライアンス遵守には,各企業が悩みを抱えている。不祥事の原因調査・再発防止策の徹底,社内での法令順守にかかわる規程作成や研修などの啓蒙活動を実施しても,不祥事が繰り返されるのはなぜだろうか。
近時,外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」または「法」という)が報道等で取り上げられる機会が増えている。国際的なM&A,半導体などの先端製品の外国への輸出,ロシアへの経済制裁などの広い場面で外為法が関係する。特に,外為法の多くの部分は安全保障を理由に対外取引を規制しているところ,昨今の経済安全保障への関心の高まりとともに,法律実務におけるその重要性が飛躍的に増している。
一方で,外為法は難解かつ長大である。複雑な条文構造や独特な法解釈を伴うことから,実務家の間でも全体像が十分に理解されているとはいいがたい。本連載では,行政官および弁護士として,外為法の改正・運用および経済安全保障政策分野の立案・法案作成ならびに企業の実務対応に携わってきた著者の視点から,全8回にわたり企業法務の観点から理解しておくべき外為法の全体像を体系的に解説する。
LEGAL HEADLINES
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業編
2025年8月,9月の法務ニュースを掲載
■政府,溶融亜鉛めっき鋼板に対するアンチダンピング調査を開始
プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会再開会合の開催
■厚労省,テレワークガイドラインおよびテレワークモデル就業規則のパンフレットを公表
■金融庁,「大量保有報告制度における『重要提案行為等』・『共同保有者』に関する法令・Q&A等の整理~機関投資家と投資先企業の建設的な対話に向けて~」を公表
■金融審議会,「第1回 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(令和7年度)」を開催
■消費者庁,ステルスマーケティング違反被疑事件で初の景表法に基づく確約計画を認定
■国交省,「マンションの再生等に係るマニュアル等の見直しに関する検討会(第1回)」を開催
■金融庁,「2025事務年度金融行政方針」を公表
■各府省庁が令和8年度の税制改正要望提出
■金融庁,「有価証券報告書の定時株主総会前の開示に関する相談窓口について」を公表
■最高裁,地方公共団体の消防職員がその部下に対する言動を理由として受けた懲戒免職処分の懲戒処分を無効とした原審判決を破棄し,処分を有効とする判断
■日米政府が通商合意を発表
■総務省,「電気通信事業分野における競争状況等の調査及び評価の実施に関する方針(案)」を公表
■内閣府,「人工知能戦略本部(第1回)」を開催
■消費者庁,将来価格を比較対照価格とした二重価格表示を有利誤認とした措置命令
ほか
最新判例アンテナ
第89回 サーバを日本国外に設置・管理しているネットワーク型システムについて,日本国内における「生産」該当性を肯定し,日本における特許権侵害の成立を肯定した事例
(最二小判令7. 3. 3裁判所ウェブサイト)
三笘 裕・江坂仁志
インターネットを利用した動画配信サイトの運営等を業としているY社は,日本国内に在住しているユーザに向けて,インターネットを通じて複数の動画共有サービス(以下「本件各サービス」という)を提供していた。
言語学の観点からみる商標実務
最終回 商標の希釈化に関する理論的・実証的考察
服部謙太朗・五所万実
「商標の希釈化(Trademark Dilution)」は,混同のおそれを伴わずとも著名表示の広告機能や顧客吸引力が損なわれる場合に対応するために導入された法理である。混同を前提としないため保護範囲が拡張する一方で,その概念はあいまいであり,実証的基盤についても十分に明らかにされていない。本稿では,記号論や心理言語学の理論的枠組みに基づき希釈化を整理するとともに,その実証的把握に向けた視座を提示する。
契約書表現「失敗ゼロ」のオキテ
最終回 リスクの言語化
藤井 塁
契約書レビューでは,何でもかんでも気になったところはとにかく修正してしまいがち,かもしれない。しかし,契約書レビューが法的リスクを回避,低減させるための作業である以上,修正作業に先立ち,なぜ修正するのかという理由(法的リスク)を言語化できるようにしておきたい。
特許ライセンスのオーラルヒストリー
最終回 SEPライセンスの歴史と展開
Jari Vaario
近年,SEP(標準必須特許)業界では,各業界におけるバリューチェーンをふまえたライセンスポイント(部品/最終製品/サービス)についての議論が活発だ。しかし,それは今に始まったものではない。セルラー規格においてライセンスポイントが最終製品となった経緯について振り返ってみたい。
投資契約における条項規定の再検討
最終回 投資の撤退等
石田 学・山下真幸
今回は,投資家がスタートアップ(発行会社)に対して投資をした後に,投資対象として不適格であること等が発覚した場合に,投資から撤退できるようにリスクヘッジする各種規定を取り上げる。このような投資の撤退等に関する条項は,ドラスティックな効果を生じさせ,スタートアップ側と投資家側の利害対立が顕在化するため,緊張度が高い。また,近年は,公正取引委員会・経済産業省が2022年3月31日付で「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(以下「本指針」という)を公表し,そのなかで「株式の買取請求権を定める場合であっても,その請求対象から経営株主等の個人を除いていくことが,競争政策上望ましいと考えられる。」と指摘されたことを受けて投資契約の規定の見直しがされるなど,特に後述の株式買取請求権を中心に注目度が高い状況にある。
なお,本連載第1回で触れた金銭を対価とする取得請求権のうち,「いつでも」行使が可能であるタイプ(随時請求型)も投資の撤退に関連するが,この点は,本連載第1回(本誌25巻8号)を参照されたい。
法務担当者のための独占禁止法"有事対応"ガイド
第2回 談合・カルテル事件の内部通報対応
神村泰輝
本連載第2回は,カルテル疑義の内部通報を受けた企業の有事対応を取り扱う。この場面は,独禁法の課徴金減免制度(リニエンシー)の存在により,有事の初動対応としての特殊性が強く,きわめて迅速な対応が必要となるため,特に備えておく必要がある。
法と人類学―法がつくられるとき―
第5回 グローバル法秩序とローカルな法文化のせめぎあい
原口侑子
前回,広義の「法」は国家法のみにあらず,法源が国内に複数ある国は多いという話をしました。今回は「非・国家法」の法規範を,超国家的な場所から見ていきます。
株主総会のDX化――壁を乗り越えるために
第3回 株主総会当日までの株主との対話
――イギリスFTSE100構成企業の取組み
須磨美月
上場会社は,株主の視点に立って,株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うとともに,株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報を適確に提供することが求められている。議決権の事前行使により株主総会当日を迎える前に決議の大勢が明らかになっていることが多く2,かつその事前の議決権行使においてPCやスマートフォンによる割合が増加しているわが国では,デジタルを活用した株主総会当日までの早期かつ充実した情報提供が重要な役割を果たすといえる。
分野別 規制改革制度のトレンドと活用法
第3回 モビリティ
荏畑龍太郎
第3回では,規制改革制度の利用実績の多いモビリティに関する規制改革制度の活用実績を紹介し,近年の傾向や特徴を紹介する。そのうえで,モビリティに関する規制改革制度の利用を進めていく際に従来利用されてきた,規制のサンドボックス制度に焦点を当て,当該制度の利用上の留意点を述べたい。
差止請求事例から考える 利用規約のチェックポイント
第4回 消費者の意思表示を擬制する条項
小林直弥・土田悠太
期間の定めのある消費者契約では,自動更新条項が定められることが多い。また,買取りサービスなどでは,消費者の所有権等を放棄させる条項が定められることもある。連載第4回では,近時の差止請求事例を紹介しながら,消費者の意思表示を擬制する条項について解説する。
統合報告書の実例から見解くコーポレート・ガバナンス
第4回 株式会社荏原製作所(荏原製作所)
天野正人
荏原製作所には,JACグループやソニーのような派手さはないが,誠実さと情熱にあふれ,顧客重視の姿勢と起業家精神を忘れないコーポレート・ガバナンスの改革と業績・経営指標の改善・成長を同時に達成した素晴らしい企業である。荏原製作所の近時の成長の歴史は,素材として優良な事業力を有しながらも,あるいは潜在的成長力を持ちながらも,足元の業績・経営指標は振るわない企業のロールモデルとなる。以下2024年版荏原製作所統合報告書を中心に言及する。
企業法務担当者のための「法的思考」入門
第9回 株主間の利益調整②
――新株発行
野村修也
新株発行は,既存株主の持株比率と株価に影響を与える。
株主の持株比率とは,発行済株式総数に占める持株数の割合であり,経営に対する支配権と結びついている。すなわち持株比率は,株主総会での発言力(議決権の割合)に直結するとともに(会社法308条),少数株主権の行使要件の具備にも影響を及ぼす(なお,分配可能額がすべて配当に回されるのであれば,持株比率の低下は株主が受領する配当額の低下をもたらすが,実務上は内部留保金の活用により配当は平準化されているので,支配比率の変動が直ちに1株あたりの配当額に影響を及ぼすことはない)。新株発行が公募または第三者割当増資の形で行われることで既存株主以外の者が株式を取得することになれば,新たに株主となった者(以下「新株主」という)が支配権を獲得する分だけ,既存株主の支配権は低下することになる。
基礎の基礎から始める要件事実・事実認定の徹底的入門
第4回 第5章 裁判規範としての民法説による立証責任対象事実(要件事実)の決定基準について(第1節,第2節)
伊藤滋夫
第4章までで述べてきたところから分かりますように,行為規範と裁判規範とでは考え方が違い,その特徴も違います。本章では,裁判規範における考え方の特徴に着目して,実際に紛争になったときに適切に対処する方法を具体的に考えていきたいと思います。
法律事務所をフル活用しよう!専門弁護士に聞くAI時代の新常識
第4回 危機管理・不祥事対応
結城大輔
連載第4回は,危機管理・不祥事対応の分野における法務部門と法律事務所の連携のあり方について取り上げる。生成AIは何を変え,何を変えないのか。危機管理・不祥事対応の難しさを乗り越える工夫はどこにあるか,探ってみたい。