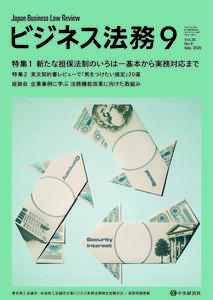
法制化の経緯と課題
阪口彰洋
従来から,動産や債権を担保化する方法として譲渡担保が用いられてきた。また,動産売買における簡易な保全策として所有権留保が用いられている。しかし,これらには,明文の規定がないため,不明確で法的安定性に欠ける面があり,譲渡担保は十分に利用されているとはいいがたかった。そこで,2021年に法制審議会担保法制部会が設置され,4年間の審議をふまえて,2025年5月30日,「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」が成立し,同年6月6日に公布された。
担保権の仕組みと基本用語
倉持喜史
担保権はその設定,維持・管理および実行の各局面において検討すべきさまざまな事柄があり,また,適用のある法律や判例上のルールも多岐にわたる。本稿では,法制化の主要ポイントを読み解くうえで前提となる担保権の基本的な仕組みおよび用語について解説する。
法制化の主要ポイント①
動産・債権譲渡担保権
大川 治・奥津 周
2025年6月6日,譲渡担保新法および整備法が公布された。これは,従前,当事者間の契約・合意で規律し,判例がその有効性を肯定してきた動産・集合動産,債権・集合債権等を担保目的とする「譲渡担保」,そして「所有権留保」を成文化するものである。法制化の背景,経緯については別稿に譲り,本稿では法制化された譲渡担保権の内容,動産,債権を目的とする譲渡担保権の効力等を概説する。
法制化の主要ポイント②
集合動産・集合債権譲渡担保権
大川 治・奥津 周
法制化の主要ポイント①に続き,本稿では法制化された集合動産および集合債権譲渡担保権の内容,対抗要件,実行手続等を概説する。
法制化の主要ポイント③
譲渡担保権の実行手続
大川 治・奥津 周
本稿では,法制化の主要ポイント①,②をふまえ,集合動産,集合債権譲渡担保権の設定を受けた債権者(担保権者)が,取引先である債務者(兼設定者)の法的倒産の申立てに遭遇した場合に,譲渡担保新法の適用下で集合動産・集合債権譲渡担保権の実行手続がどうなるか,法的倒産の開始によって譲渡担保権がどのように取り扱われるかをモデルケースに基づいて時系列的に概説する。
法制化の主要ポイント④
所有権留保
髙井章光
所有権留保につき,今回,新たに法律によってその内容が規定された。これまでその法的性質について争いがあったが,譲渡担保新法では担保権として規定され,動産譲渡担保権の規定が準用されることになった。なお,対抗要件については「売主への引渡し」が必要とされるが,被担保債権と牽連性がある場合(いわゆる狭義の所有権留保)には,原則として「引渡し」がなくても第三者に対抗できるとされている。
法制化の主要ポイント⑤
企業価値担保権
倉持喜史
企業価値担保権は,2024年に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」により新たに導入された担保制度であり,従来の法制度の下では担保権の設定が困難であった無形資産等についても担保価値を認めた資金調達を可能にするものである。同法は2026年5月25日に施行予定であり,目下,施行に向けた準備が急ピッチで進められている。
新たな担保法制をふまえた実務への影響
末廣裕亮・松井裕介
譲渡担保新法や企業価値担保権の創設は,担保付融資の実務に大きな影響を与える。譲渡担保新法は,譲渡担保を利用する与信の取組みに影響を与え,契約内容や対抗要件等に関する現行実務の見直しを要する。また,譲渡担保権の実行方法や担保権者による組入義務等の新しい規律が,債権回収の実務に影響を及ぼすことも予想される。企業価値担保権は新しい制度であり,組成から実行に至る各段階につき,実務の観点から検討が必要となる。
鈴木馨祐
5月にウズベキスタン,キルギスに出張した。ロシア,中国に挟まれた地に位置する中央アジアに対する主要国の地政学的な関心が近年高まっている。そんななか,法務省はウズベキスタンに対しては独立後間もない時期から,キルギスに対しては昨年度より,法制度整備支援を行っている。
総論――英文契約書に向き合うにあたって
遠藤聖志・稲葉正泰・東崎雅夫
英文契約書は,日本語の契約に比べ,一般的に個々の条項が長くかつ複雑であり,普段見ないような法律用語も使われることが多いことから,全体的にわかりにくく,比較的経験の浅い法務部員がいきなりレビューしても,どこをどう直せばよいかわからず苦労することが多いと思われる。
表明保証
戸田隆寛
表明保証条項とは,契約の当事者が,一定の時点において一定の事項が真実かつ正確であることを契約相手方に対して表明(representation)および保証(warranty)という形式で約束する条項をいい,契約当事者が特に重要と考える事項を確認する目的で英文契約書において広く用いられる。特にM&A取引においては,買主が売主に対して,対象会社の存続,事業,資産等に関する広範な表明保証を求めることが一般的であり,契約書のレビュー,交渉における重要なポイントの1つとなる。
クロージングの前提条件
前川 萌
前提条件(conditions precedent)とは,契約書上の義務が当事者に対して拘束力を持つための前提となる条件であり,M&A契約においては,クロージングをする前提として充足すべき条件を合意する条項で,主要な取引条件の1つである。
補償条項
丹羽達也
補償(Indemnity)条項とは,一方当事者が,当事者間で合意した一定の事由が生じた場合に,当該事由により他方当事者が被った損害について,合意された金額を支払うことにより填補することを約束する条項である。M&A取引においては,誓約事項や表明保証の違反の場合やデューデリジェンスを通じて発見された問題点が具体的な損害として実現した場合を補償条項の発動事由として,売主に補償義務を負わせる合意をすることが多い。
責任の制限
柏原敬俊
当事者が負う損害賠償義務や補償義務が無制限に広がることを回避するため,その範囲,金額,期間などの観点から一定の制限を設ける旨が合意されることがある。日本と同様,海外の法制度においても損害賠償の範囲や期間制限については判例法や成文法で一定のルールが置かれているのが通常であり,準拠法その他適用法下における原則的なルールを事前に調査・理解しておくことが重要であるものの,賠償義務の範囲や期間を予測可能なものとするという観点では,それらについて当事者間で明確に合意しておくことも重要である。
契約終了・存続条項
柏原敬俊
契約の終了という効果の重大性から,契約終了(Termination)条項は契約交渉において最も争点となりやすい条項の1つである。条項例に記載の重大な契約違反および相手方の倒産・支払不能は最も典型的な終了事由の1つであるが,その他にも相手方の支配権の変動(チェンジオブコントロール),不可抗力または関連する他の契約上の違反(クロスデフォルト)を終了事由とすることもある。
秘密保持
岡田次弘・近藤友紀
秘密保持条項は,一般的に,契約当事者がその契約に関連してまたはこれに基づき受領する情報が秘密に保持されることを定める条項である。通常,営業秘密を知的財産権として保護する要件として,その情報の秘密保持を目的とした合理的手段が求められるため,適切な秘密保持条項の合意は,かかる要件を満たすためにも重要である。
知的財産権
岡田次弘・近藤友紀
契約当事者間で知的財産権に関して合意すべき最も基本的な事項として,その帰属と利用(ライセンス)条件がある。条項例は,それらを定める製品の製造委託契約の条項である。
競業避止義務
大倉準哉
競業避止(non-competition)条項とは,契約の一方または双方の当事者に対し,競業避止条項で定める事業と同一または類似の事業(競合事業)等を直接または間接に行うことを禁止する条項であり,競業避止条項の対象者が自然人である場合には,その自然人が,競合事業を行う事業者の役員または従業員となることを禁止する条項を含むこともある。
勧誘禁止義務
大倉準哉
勧誘禁止(non-solicitation)条項とは,一方の当事者が,契約相手方の従業員等を勧誘し引き抜くことを禁止する条項であり,ビジネスにおける取引関係を円滑に保ち,人的資源の流出を防ぐために用いられる条項である。
不可抗力
東崎雅夫
不可抗力(Force Majeure)条項とは,当事者がコントロールできない事情(火災,洪水または地震等)によって自己の債務を履行できない場合に債務不履行責任を免れることを規定する条項である。
最恵国待遇
長尾理沙
最恵国待遇(Most Favored Nation)条項とは,当事者が契約相手方に対し,自己との契約条件について,契約相手方が第三者に提示する契約条件と同等か,またはより有利な条件となるよう確保させることを目的とした条項である。もともとは国家間の条約において古くから用いられてきた概念であるが,現在では供給契約,ライセンス契約,プラットフォーマーとの契約,投資契約等の企業間の取引契約の場面でも使用されることがある。
製造物責任(リコール対応等)
東崎雅夫
一般的に,製造物責任とは,製造物の欠陥により第三者の生命,身体または財産に損害を与えた場合に,製造業者等が被害者に対して負う損害賠償責任を意味する。当事者間の契約において準拠法を定めたとしても,製造業者等と第三者である被害者との関係においては,該当する法域の製造物責任法およびその関連法令(以下「現地法令」という)が適用されることになり,現地法令によっては,損害賠償責任に加え,製造業者等(輸入者を含む)による政府機関等に対する報告書の提出またはリコール対応等が必要となる。
分離可能性
大倉準哉
分離可能性(severability)条項とは,意図していた契約内容の一部が適用法の強行法規に抵触し無効とされる場合であっても,他の条項の有効性については影響を与えない旨を規定する条項である。これに加え,無効となった規 定についても,契約締結時の両当事者の意図にできるだけ即した有効な内容となるよう両当事者間で協議する旨規定する場合もある。
費用負担
稲葉正泰
契約書の作成,交渉および調印,ならびに契約を履行するために必要となる費用(外部弁護士の費用,税金など)をいずれの当事者の負担とするかを明確にする目的で,費用負担条項が合意される。
完全合意
戸田隆寛
完全合意(Entire Agreement)条項とは,事前の交渉や合意内容にかかわらず,契約書に規定された内容が当事者間の最終的かつ完全な合意内容であることを明示する条項である。英米法のもとでも,日本法と同様,書面によらずとも契約自体は成立し,口頭での合意であっても原則としては相手方に履行を強制することができる。もっとも,仮に書面での契約を締結したとしても,相手方が別途,契約書に記載されていない条件や合意事項が存在する旨主張することが認められるとすれば,書面で契約を締結した意味が薄れる。
譲渡禁止
丹羽達也
譲渡禁止(no assignment)条項とは,契約上の地位(または契約上の権利義務)について,相手方の承諾のなく第三者に譲渡することを禁止する条項である。相手方の信用や履行能力等に依拠して契約関係に入ったにもかかわらず,意図せずにその相手方が変更されれば重大な影響を受けかねず,また過誤払いの危険等も生ずる可能性があるため,契約において譲渡禁止条項を定めるのが一般的である。
通知条項
長尾理沙
通知条項は,契約に基づきまたはそれに関連して行われる当事者間での通知や連絡について,どのような方法をとった場合に,いつの時点で契約上有効なものとしてその効果が生じるかを規定することを目的としている。
準拠法
吉田武史・桒原里枝
準拠法条項(Governing Law)とは,契約に関連する法的解釈をする場合に,どの法域の法律を基準とするか指定する条項である。予測可能性を高めるうえでは,準拠法指定の客観的範囲を広くかつ明確に指定しておくべきであり,条項例では,契約の成立,有効性のみならず,契約および契約から発生するまたはこれに関連するすべての契約外の義務の履行についても,準拠法指定の範囲として明記している。
裁判管轄
吉田武史・山内理恵子
裁判管轄は,いずれの法域であっても,当事者間における専属管轄の合意がない限り,法律によって決定されるのが通常である。もっとも,契約締結時に予期していなかった法域での裁判を強いられないようにするため,海外の当事者との英文契約において裁判管轄条項を規定することは日本の当事者間の契約と 比較してより重要である。
仲裁条項
吉田武史・山内理恵子
仲裁は当事者間の合意があって初めて利用可能となる紛争解決手段である。そのため,事前に契約書で仲裁条項を定めておくことが望ましい。
渡辺大祐
消費者庁は,2024年4月18日に「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年4月1日事務局長通達第7号)を改定し,買取サービスが不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律134号。以下「景品表示法」という) の規制対象になりうることを明確化した1。
川井信之
2024年10月1日から,商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され,代表取締役等住所非表示措置がスタートした。
中野進一郎
昨今の医薬品の供給不安やいわゆるドラッグ・ロス問題等を背景に,改正薬機法等が成立した。今回の改正では,前回の法改正時に見送られた責任役員変更命令の法定化,医薬品の安定供給のためのガバナンスの強化,医薬品リスク管理計画(RMP)の位置づけ変更等が行われた。医薬品開発に関する事項では,米国FDAをはじめとした海外の規制・制度を参考に,承認事項の変更手続の合理化や創薬環境の改善が試みられている。また,医薬品の販売環境の変化に伴い,薬局等に関する規制等も改正された。
非業務執行役員へのインセンティブ報酬導入の実務
金井悠太
コーポレート・ガバナンス改革の進展に伴い,業務執行役員へのインセンティブ報酬制度の導入が一般化する一方で,社外取締役等の非業務執行役員への導入は,株主との目線の共通化といった観点から検討には値するものの,いまだ過渡的な状況にある。
本稿は,非業務執行役員へのインセンティブ報酬の導入に際して留意すべき法的論点と投資家側の視点を整理し,その検討に向けた一助とすることを目的とする。
金久直樹
本書は,オックスフォード大学教授などを歴任し,40 年間にわたりAI が社会や専門職に与える影響を研究しているリチャード・サスキンド氏による最新の著作となる。同氏が2023 年に出版したTomorrow's Lawyers: AnIntroduction to your Future の第3版(邦題『明日の法律家』)は,世界中の多くの法律家に衝撃を与えたが,それに続く本書は必ずしも法律家のみを対象にした内容でなく,AIについて今一度現状を整理し,深く考察したいと考えているすべての人に向けられた内容となっている。もちろん長年にわたり法律家の未来について研究している著者からわれわれ法律家に向けられた多くのメッセージも含まれている。
PICK UP 法律実務書 『明日の法律家』
板谷隆平
本書の原著は,リーガル業界におけるテクノロジー活用の先駆的提唱者であるリチャード・サスキンド氏が,業界全体の現状をふまえ,法律家の将来像を描き出す意欲作である。原著は第3版だが,パンデミック後の状況や生成AIなどの最新テクノロジーをふまえて前版より大幅に内容が刷新された。
PICK UP 法律実務書 『Q&A フリーランス法の解説』
滝澤紗矢子
本書は,フリーランス法制定に係る検討会委員であった経済法と労働法の研究者を中心に,これらの実務を専門とする中堅気鋭の弁護士が加わって執筆された,フリーランス法の実務的解説書である。フリーランス法に対応する企業の担当者だけでなく,本法により保護されるフリーランス本人にも活用されることを望んでいる,と編者は説明している。すなわち,必ずしも法律に親しみのない読者層も想定されている。フリーランス法規制において,この想定は現実的重要性をもつ。
小林直弥・土田悠太
本連載では,適格消費者団体による近時の差止請求事例を素材として,BtoC事業を行う企業の法務担当者等が,利用規約の内容を検討する際のチェックポイントを解説する。第1回では,差止請求訴訟制度と消費者契約法における不当条項規制について概観し,第2回以降では,近時の差止請求事例を紹介しな がら,個別の論点について解説する。
LEGAL HEADLINES
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業編
2025年5月,6月の法務ニュースを掲載
■労働安全衛生法等の一部改正法が成立・公布
■公取委,スマホソフトウェア競争促進法に関する指針案等の意見募集実施
■国税庁,非財務指標を組み入れた業績連動型株式報酬の税務上の取扱いに関する文書回答事例を公表
■「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」が成立
■金融庁,有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた施策等の一覧等を公表
■SSBJ事務局,2025年5月SSBJハンドブックを公表
■SSBJ,中期運営方針を公表
■政府知財戦略本部,「知的財産推進計画2025」を決定
■洋上風力発電に関する法律の対象を領海内からEEZに拡大する改正法が成立
■「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI法)が公布
■「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」が公布
■公取委,「生成AIに関する実態調査報告書ver.1.0」を公表
■「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」が成立
■環境省,令和7年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書を公表
■DOJ,米国FCPAの執行再開と新ガイドラインを公表
■公益通報者保護法の改正法が成立・公布
■日本製鉄によるUSスチールの買収をトランプ大統領が承認
悔しさを糧に――学べば開ける☆
最終話 震災のあった年に起きた,ごくごく私的な出来事から......
木山泰嗣
絵本のような,憲法の物語を描きたい。そんな思いで,時間をかけて執筆したのが『憲法がしゃべった。』(すばる舎,2011)でした。「印刷所に提出してきました。ベストセラーになると思います」そんな内容のメールを,夜遅くに担当編集者からもらいました。その翌日,東日本大震災が起きました。震災後に発売されると,出版社が新聞の下1面に大きな広告を出稿してくれました。原子力発電所の事故などの未曾有の災害のさなかです。発売日の夕方,仕事を終えて事務所を出ると,新宿の紀伊國屋書店に向かいました。驚くほどたくさん並べられていました。ですが,節電で薄暗い書店に,人影はありませんでした。
「eスポーツビジネス」法的論点と対応
最終回 不測の事態への対応と選手契約の留意点
小石川 哲・加藤滉樹
本稿では,スポンサー企業と選手,チームと選手,それぞれの契約関係における留意事項に言及しつつ,eスポーツ競技について生じうる不測の事態への対応とその留意点について検討する。
特許ライセンスのオーラルヒストリー
第2回 MPEG-2特許プールライセンスとその教訓
福岡則子
MPEG-2は,デジタル映像技術の標準化を目指して1990年代初頭に策定された国際規格であり,その普及には標準必須特許(SEP)の取扱いが重要な課題となった。本稿では,MPEG-2特許プールの設立背景,運営方法,そして市場への影響について詳述し,技術標準化と特許管理の成功事例としての教訓を探る。
最新判例アンテナ
第86回 すし店を営む原告の商標と類似の表示を被告ウェブページに掲載する行為について,すし店に関する「役務に関する広告」に当たらないとして,商標権侵害が否定された事例
(知財高判令6.10.30金判1708号14頁)
三笘 裕・大野開士
原告X社(日本において,すし店経営などを行う会社)は,被告Y社(魚介類および水産加工品の輸出入等を行う会社であり,グループ会社に,マレーシアにおいてすし店を営むA社がある)に対し,Y社がウェブページにおいてX社が経営するすし店の名称に類似した表示を掲載した行為およびSNSのアカウントに同様の表示を含むプロフィール写真を掲載した行為につき,不正競争防止法(以下「不競法」という)2条1項1号または2号の不正競争に該当し,X社の商標権の侵害(商標法37条1号)にも該当すると主張して,不競法3条1項または商標法36条1項に基づく表示の差止めおよび削除を求める請求ならびに不競法4条または民法709条に基づく損害賠償を求めて訴訟を提起した。
法と人類学―法がつくられるとき―
第2回 法人類学の可能性
藪本雄登
原口さんが第1回で提示された「法人類学(Law and Anthropology)」の概説では,国民国家主義,西洋中心主義,そして男性中心主義によって構築されてきた「法律」という概念の限界が示されました。この問題提起には,私も深く共感します。アジアの現場で実務を行うなかで感じるのは,現代のグローバル高度資本主義のもと,世界中で画一化された経済理論や政策に基づいて,同様の投資・経済法制が整備されていくという現実です。たとえば,『南アジアの法律実務』(中央経済社,2021)を執筆した際,会社法,労働法や個人情報保護法などといった主要な法制において,南アジア諸国の法制度間の差異が少なくなりつつあることを痛感しました。
投資契約における条項規定の再検討
第2回 発行会社の運営のコントロール
石田 学・山下真幸
投資契約では,スタートアップ(発行会社)が適切に運営され,IPOやM&Aというエグジットに向けて健全に発展すること等を目的に,会社運営に関するルールが定められる。今回は,このような発行会社の運営のコントロールに関する条項の交渉例について解説する。
統合報告書の実例から見解くコーポレート・ガバナンス
第2回 株式会社ジェイエイシーリクルートメント(JACグループ)
天野正人
JACグループは,世界と戦い勝ちに行ける,日本で有数の優良企業であり,起業家精神あふれる企業文化はスタートアップ企業のロールモデルであり,業績・経営指標も素晴らしい。JACグループの統合報告書は,最初の10頁を読むだけで,投資家の関心対象である重要な企業情報が鳥瞰的に把握できる優れたものであり,さらにこれに引き続く10数頁を読むだけで投資家は凝縮されたIR情報が得られるように工夫されている。以下,JACグループ2024年版統合報告書をもとに言及する。
言語学の観点からみる商標実務
第3回 同音異義語の類否
堀田秀吾・服部謙太朗
商標法における商標の類否判断は,取引の実情をふまえ,「外観」「称呼」「観念」という3つの観点を中心に出所の誤認混同を生じるおそれがあるかを判断するが,実際の消費者の言語認知過程では,これらの要素が複雑に相互作用している可能性がある。本稿では,この点に着目し,同音異義語を事例とする言語認知の知見を商標判断に応用する可能性を探る。このような考察により,より客観的かつ実証的な判断基準の構築に寄与しうると考える。
契約書表現「失敗ゼロ」のオキテ
第8回 続・条件(悪魔の証明)
藤井 塁
法的効果の発動条件として,あることがらが「存在しない」ことを定めている場合がある。たとえば,次のような規定である(デッドロックのようなケースをイメージしてもらいたい)。
ライアン・ゴールドスティンの"勝てる"交渉術
第17回 上司のあなたに贈る部下との関係性の築き方
ライアン・ゴールドスティン
とある企業のトップと話をしたときに,実に共感したことがある。「最近の若い者は......と,昔は年配者によく言われ,その言葉に反発を覚えた。自分はそんな目で若手を眺めないと心に決めた。それなのに,若手と自分の見解が違うと,心のどこかで最近の若い者は......と思ってしまう」そのトップはそんな自分を省みて,もっとフラットな視点で若手を理解したいと考えているというのだ。
私も当然のことながら,若手の弁護士たちとも仕事をする。そのうえで,良好な関係を築き,仕事をうまく運びたいと常々努力している。今回は直接的な交渉術ではないが,一体感のあるチームとなってビジネスを進めるための上司としてのあり方を考えたい。
テーマ別「インバウンド法務」の勘どころ
第4回 不動産
増山 健・古田俊文
本連載では,インバウンド法務を日々取り扱う弁護士らが,対談形式でテーマごとに案件の特徴や問題点等について語る。今回は,不動産の分野について取り扱う。
〈業種別〉テクノロジー法務の最新トピック
第5回 モビリティ
殿村桂司・小松 諒・水越政輝・松﨑由晃
近年の生成AIの普及にみられるように,新たなテクノロジーの活用はあらゆる業種において急速に進んでおり,それに付随して業種ごとに異なる新規かつ複雑な法的問題が生じ,また,各国における法制度の見直しも急ピッチで進められている。本連載では,テクノロジー法務を扱う弁護士が,各業種について知見を有する弁護士とともに,業種別のテクノロジー関連の最新トピックやそれらを検討する際の実践的な視点を紹介する。
第5回は,モビリティ業界について取り扱う。
当局のプラクティスから学ぶ米国法
第3回 デジタル社会におけるグローバルコンプライアンス
――21世紀のデジタル立入検査
ティム・ハワード・上林祐介
クラウドサービスの普及に伴い,日本企業が国際的な調査の対象となるリスクが高まっている。本稿では,米国のSCA法およびCLOUD法の概要を解説するとともに,日本企業が導入すべきグローバルなコンプライアンス対策を考察する。
マンガで事例紹介!
フリーランスにまつわる法律トラブル
第11話 トラブルの予防策
宇根駿人・田島佑規・ CS合同会社
フリーランスと企業との間において契約書を締結することは,業務委託における基本的なトラブル予防策であることに異論はありません。
企業法務担当者のための「法的思考」入門
第6回 配当政策とマルチタスク問題
野村修也
他人資本と自己資本の割合を一般に資本構成と呼ぶ。資本構成が企業価値や株価にどのような影響を及ぼすのかは,財務戦略上の重要テーマの1つである。
デジタルマーケティングの法律相談
第4回 個人情報保護法③
――第三者提供の諸論点(同意・記録・共同利用)
寺門峻佑・林 知宏・榊原颯子・牧 昂平
本稿では,デジタルマーケティング施策において個人データの第三者提供が行われる場合に,望ましい同意文言のあり方や提供記録・確認記録の作成の手法を紹介するとともに,第三者提供規制の例外や(その一類型である)共同利用における論点について解説する。
Airbnbで学んだ「法務の時間術」6つの金貨
第5回 疑え,法務部の複数名が招待
された会議
渡部友一郎
「法務が3人も4人も出席する会議は何かおかしい」
法務部門で働く方であれば,一度は経験したことがあるでしょう。会議に招待され,出席してみると,実は自分の担当とはさほど関係のない内容だったり,単なる情報共有が目的で参加を求められていただけだったりすることがあります。こうした状況が続くと,無駄に浪費される時間が積み重なり,本来集中すべき業務に影響を及ぼします。なかには,議事録を後から確認すれば十分だった,というケースもめずらしくないでしょう。また,「社内会議白書2023 by MeetingBase」によれば,「会議に必要ない参加者がいる」と感じる人の割合は52.2%に達しており,社内会議中に無駄だと感じることが「ある」人の割合は88.8%を記録しています。