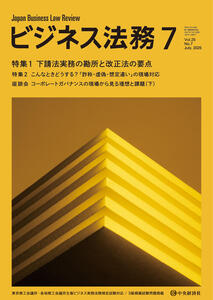
下請法実務の勘所と改正法の要点
基礎知識の再点検⑴
――法の適用範囲
森 悠樹
近時,下請法違反を理由とする公取委の執行事例が,過去に例をみない頻度で多数公表されている。このような執行状況は,下請法違反に対してこれまで以上に積極的かつ幅広く厳正に対処しようとする公取委の姿勢がうかがえるが,企業が下請法コンプライアンスを浸透させ,勧告をはじめとする違反リスクを低減するには,法務担当者が中心となって,下請法の全体像と各規制のポイントを押さえ,自社にとってのリスクの軽重に応じて違反防止策を講じておくことが肝要である。
そこで,本稿と次稿では,「今さら聞けない」と思われがちだが,実務上は重要な下請法の基礎知識をQAを交えながら紹介し,下請法規制の勘所を解説する。
基礎知識の再点検⑵
――親事業者の義務と禁止行為
森 悠樹
前稿に引き続き,実務上重要な下請法の基礎知識についてQAを交えながら紹介する。本稿では,下請法規制の具体的内容である親事業者の義務および禁止行為を取り扱う。
改正法の概要と影響⑴
――法案の全体像,運送委託,従業員基準
武井祐生
2025年3月11日,下請法の改正法案(以下「改正法案」という)が閣議決定された。現在開会中の第217回通常国会に提出されており,政府は今国会での成立を目指すとしている。施行期日は2026年1月1日とされているため,改正法案が成立した場合,本年中には改正法への対応が必要となる。
下請法の適用範囲が拡充され,禁止行為も追加されるなど実務への影響も小さくないと見込まれ,本稿では,改正法案の内容と予想される影響について解説する。
改正法の概要と影響⑵
――価格転嫁,手形の取扱い
武井祐生
本稿では,前稿に引き続き,改正法案の内容と予想される影響について解説する。
ケーススタディで考える有事対応⑴
――対応の全体像,下請事業者による金型の無償保管
前田啓太
本稿では,公正取引委員会(以下「公取委」という)または中小企業庁(以下,公取委とあわせて「公取委等」という)により,下請法違反を理由とする立入検査がなされた場合や社内調査等により下請法違反が発覚した場合に,企業が講じるべき対応の全体像を概観するとともに,下請法に関する近年のトレンドもふまえ,特に重要と考えられる違反類型ごとに,法務担当者として押さえておくべき有事の対応策やポイントについて,ケーススタディを交えて解説する。
ケーススタディで考える有事対応⑵
――価格転嫁,割引困難な手形の交付,代金減額
堀部道寛
本稿では,前稿までで取り上げた近時の公正取引委員会(以下「公取委」という)の執行状況や,下請法やガイドラインの改正動向等もふまえ,下請法違反が判明した有事における具体的な対応方法につき,実務上問題になりやすい価格転嫁(買いたたき),割引困難な手形の交付,代金減額の各類型に関するケーススタディを題材として解説する。
若狭 勝
どこに向かうのか,「信頼が厚い専門家の職業倫理」!
長き検事の仕事で思ったことがある。それは,「感情の生き物」である人間は,誰でも,心の奥底に魔物が潜む。もとより人によって魔物の質や量の正体は異なる。魔物が心の中で増殖しだすと,ある時,第三者には決して理解できない形で犯罪等の行動に及ぶことがある。
高井伸太郎/大宮 立
TXL法律事務所(以下「当事務所」という)は,2016年7月に設立された「高井&パートナーズ法律事務所」と,2018年10月に設立された「レックス法律事務所」が経営統合し,2024年7月にスタートした,企業法務を主たる業務分野とする法律事務所である。
以下では,法律事務所が統合する際の留意点について,筆者らの経験に基づき説明する。
高橋 均/藤原幸一/淵邊善彦/星野悠樹/(司会)久保田真悟
本座談会では,企業不正やリスク管理体制の不備に起因する企業価値の毀損を防ぐために必要な経営レベルでの取組みを検討し,最後に,座談会(上)の内容も含めて取締役会が高いパフォーマンスを発揮するうえで欠かせない存在である取締役会事務局のあり方を探っていく。
「詐称」対応の心構え
――事実関係の把握と社内外に向けた対応
木山二郎
「詐称」とは,住所,氏名,年齢,職業,学歴等を詐って称することなどと定義されている。企業においては,たとえば,契約上,自社の製品やサービスの品質・性能等を保証することがあるが,その前提となる品質・性能等を詐称するといったことはあってはならない。
入社後に発覚した経歴詐称
中野博和
当社において6年前に中途採用で入社した社員について,入社後特段の問題を起こすことはなかったものの,入社前に傷害事件を起こして服役していたことが判明した。履歴書には賞罰欄はなく,採用面接時においても犯罪歴を確認しなかったものの,当社としては,傷害事件を起こしたにもかかわらず,このことを採用過程で告げなかった当該社員を信頼して働かせることはできないと考え,弁明の機会を与えたうえで懲戒解雇とした。懲戒解雇は有効と認められるか。
システムエンジニアリングサービスと経歴詐称
増田拓也
中堅メーカーである当社は,幅広くSES事業を展開するS社と契約を締結した。翌月以降,S社の従業員であるN氏が,当社オフィス内に常駐して勤務することになった。S社の営業担当者は,N氏について「JavaでのWebアプリ開発経験5年のエンジニア」と説明した。ところが,実際にN氏が勤務を開始すると,当社の従業員たちから,「N氏は簡単なテストもできない」などの苦情が頻繁に出るようになった。
そんな中,当社のWebアプリ開発部門の責任者宛に,N氏から次のメールが届いた。
取引条件の不実表記
和田圭介
A社は,特殊な物品の調達に関して,B社に発注し,前払いで代金を支払った。B社を選んだ理由は,有利な価格と短納期であったが,B社が提示した「特別割引価格」は実際には適用条件を満たさないため,適用されず,「短納期」も実現不可能なものであった。にもかかわらず,契約後,B社は「特別割引価格」の適用条件を満たしていないとして大幅な追加の代金請求をしたうえで,残りの金額が支払われない限り,作業を進めないと通告してきた。A社はどのような対応をとるべきか。
商品・役務の取引に関する景表法違反
森 瑛史
【設例①】A社は,サプリメントXに痩身効果がないことを知りながら,痩せるとの表現は直接使用しないものの,痩身効果があると誤解させるべく,「昔履けたズボンが履けるようになった」「飲み始めてすぐ」等という表現とともに,やせ型のモデルを用いた写真を多数載せ,あたかもXに痩身効果があると一般消費者が誤解する商品説明を付して,Xを販売した。
【設例②】A社は,Xの販売実績を作るため,3日間だけ「通常価格16,500円(税込)」と表示して販売活動を行い,その後,「通常価格16,500円(税込),今だけ5,500円(税込)」と併記してXを販売した。
品質不正の初動調査と原因究明
荒井喜美/藤尾春香
法令により認証を取得している工業製品の部品の製造業を営むX社の内部通報窓口に,同社従業員より,「A製品は,強度に関する検査データが偽装されて,最終製品を組み立てる取引先に出荷されている」との内部通報があった。A製品が組立てに使われた製品は,国内外に出荷されている。通報者は,人事異動によりA製品の製造工程担当者であり,前任者から引き継いだ際に,検査データの偽装を知ったとのことである。
スタートアップ投資契約における表明保証違反
西口健太
スタートアップ企業A社がベンチャーキャピタルB社から増資新株の発行による3億円の資金調達を行った。その際の投資契約においては,A社においてパワハラその他法律違反となるような労働関係は存在しない旨の表明保証条項が規定された。しかしながら,同投資契約のクロージング後,A社の経営幹部が以前から従業員に対するパワハラを繰り返し,複数の従業員が心身を故障し離職していたことが判明した。
共同開発案件における想定違い
重冨貴光
A社は,顧客との受発注・請求・回収業務処理を効率化するシステム開発を企図し,複数のシステム開発業者にシステム仕様(A社事業特有の取引の仕組みへの対応を含む仕様)を提示し,引合いを行った。システム開発業者であるB社は,A社との取引獲得・拡大を目指し,他の業者よりも格段に廉価・早期にてシステム仕様を実現することが可能であるとのプレゼンテーションを行った。A社は,B社のプレゼンテーションを受け,廉価・早期にて要求仕様の実現が可能であると想定し,B社との間でシステム共同開発契約を締結した。
しかるに,B社はA社事業特有の取引の仕組み詳細を十分に理解していなかったため,要求仕様に即したシステム開発を行うことができず,さらには契約締結後に開発事業部の主力人員の退職が相次いだため,納期を過ぎてもシステム開発は一向に進捗せず,システム開発は進捗半ばにて頓挫した。B社の開発作業結果は使い物にならず,A社は,別のシステム開発業者との共同開発のあらためての実施を余儀なくされた。
SNSにおける虚偽情報の流布への対応
清水陽平
SNSに「購入したお菓子に虫が入っていた!」というコメント,「#異物混入」というハッシュタグとともに,その様子を写した写真が投稿された。投稿は写真のインパクトもあり一気に拡散され,多数のまとめサイトも作られ,地図アプリのコメント欄には「虫入りお菓子を製造する不衛生な工場です」といった投稿まで行われてしまっている状態である。
経営陣の責任問題に波及する場合とその対応
田中 敦
企業が詐称行為に関与した場合,役員が法的責任を問われることがある。たとえば,株主や消費者への虚偽報告が明らかになると,役員個人として損害賠償責任や刑事罰を負う可能性がある。また,企業が詐称行為の被害にあった場合であっても,役員の責任が問われることがあり,詐欺メールによる送金指示に漫然と従った事例で代表取締役の責任が肯定されたケースが存在する。
企業としては,詐称行為による損害が生じることを防ぐために,内部統制やリスク管理の強化を進めるべきであり,役員個人としても,任務懈怠責任を負わないために,積極的な情報収集と慎重な対応が求められる。
大澤加奈子
2025年3月,「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案」が国会に提出された。動産・債権の譲渡担保契約の効力から実行まで,および所有権留保契約を成文化するものであり,担保権者および設定者双方に大きな影響を与える法案である。
「公益通報者保護法の一部を改正する法律案」の概要
西本良輔/奥田敦貴
内部通報制度は,企業の不正・不祥事を未然に,または早期に把握し,是正を図るための仕組みである。昨今,その意義は一段と高まっているが,内部通報をちゅうちょし,または断念する者も少なくなく,その実効性に関しては引き続き課題が多い。これらの課題を解決すべく,今般,公益通報者保護法の改正法案が国会に提出された。本稿ではその内容について概説する。
「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロ責法)」新規律に関する実務上の留意点
板倉陽一郎
本稿では,①情プラ法の義務の対象である,大規模特定電気通信役務提供者,②大規模特定電気通信役務提供者における侵害情報送信防止措置を申し出る,申出者,③侵害情報の対象ではないが,侵害情報についての申し出を行う,被侵害者以外の者のそれぞれの観点から,実務上の留意点を述べる。
LPS法改正とファンド・CVC実務の留意点
飯島隆博
2024年6月,組合型のコーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)を含むVCやプライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)において用いられる投資事業有限責任組合(LPS)について規律する,投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)の改正が行われ,2025年4月1日までに施行された。当該改正では,LPSによる海外投資上限規制の緩和や,暗号資産や合同会社の持分の取得等が認められている。本稿では,当該改正やそれを受けたファンド実務の動向を解説する。
岡芹健夫
何とも景気の悪い話題ではあるが,昨年より今年にかけて,相当規模の人員削減の話題がメディアに散見されることが増えてきた感がある。2025年1月10日付日本経済新聞電子版によれば,2024年の早期・希望退職募集の総数は,1万人を超えたとのことである。
LEGAL HEADLINES
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
2025年3月,4月の法務ニュースを掲載。
■金融庁,「記述情報の開示の好事例集2024」最終版を公表
■厚労省,「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」を公表
■金融相,全上場会社に対し「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」を通知
■法務省,令和8年4月1日以降の法定利率について告示
■GPIF,「サステナビリティ投資方針」を制定
■公取委,スマホ競争促進法に基づく特定事業者を指定
■所得税法等の一部を改正する法律が成立
■環境省,「令和6年度版グリーンファイナンスによる資金調達を行った企業の取組事例」を公表
■経産省,「営業秘密管理指針」を改訂
■総務省,「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けのガイダンス(案)」を公表
■商米トランプ政権,相互関税を発表
■金融庁,「立替サービスの貸金業該当性に関するQ&A」を公表
■公取委,企業結合計画の届出書記載要領を改訂
■消費者庁,「いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査」のリサーチ・ディスカッション・ペーパーを公表
■金融庁,「『暗号資産に関する制度のあり方等の検証』ディスカッション・ペーパーの公表について」を公表
■東証,MBO・支配株主による完全子会社化に係る規範の見直し案を公表
西村雅子/堀田秀吾
商標は,文字,図形,記号,立体的形状等からなり,多くは文字,すなわち言語からなるところ,これまで言語学において商標はメジャーな研究対象ではなく,他方,商標の研究分野でも言語学は,ほとんど考慮されてこなかった。本連載では,商標の研究者および実務者と言語学の研究者のコラボ企画として,商標実務上,常に問題となる類否判断や識別力の有無の判断などについて,問題提起と言語学の観点からの提言という形式で,具体例を挙げて検討したいと考える。その目的とするところは,将来的に「言語学的根拠に基づく客観性や説得性のある判断基準を示し,より安定した行政・司法判断へと繋げること」であり,本連載は知財法務のなかで悩ましい商標事例の判断の一助となることを目指すものとする。
最新判例アンテナ
第84回 いわゆるデッドロックの状況にある株式会社の解散請求が認められなかった事例
(東京高判令6.10.9金判1708号38頁)
三笘 裕/片瀬麻紗子
本件は,XとAが50%ずつ株式を保有する株式会社Y社について,会社法833条1項各号に該当し,かつ,株主総会および取締役協議がデッドロックの状況にあり,事態を打開するのに解散判決以外に公正かつ相当な手段がないから,同項柱書の「やむを得ない事由」があると主張して,XがY社を解散するよう求めたところ,第1審がXの請求を棄却したので,Xが控訴した事案である。
経営の一翼を担う法務――CLO/GCの役割と実践
最終回 CLO/GCが発揮すべき役割(各論:後編)
――負うべき役割を具体例で示す
今仲 翔
本連載の最終回では,第4回に引き続き,企業活動においてCLO/GCがどのような役割を担うべきかについて,具体的なケースに基づき実務上の参考例を示すこととする。本稿では,具体例として,全社的リスクマネジメント(ERM),決裁基準の策定,M&Aを題材に取り上げたうえで,それらを実行する場面でのCLO/GCの役割を述べる。
契約書表現「失敗ゼロ」のオキテ
第7回 条件
藤井 塁
契約書の解釈でよく争いになる論点の1つに,法的効果の発動条件が満たされているかどうかというものがある。特に,支払いや返金に関する条項で問題になることが多い。
「パーソナルデータ」新しい利活用の法律問題
最終回 パーソナルデータの新しい利活用の今後
木村一輝
本連載ではパーソナルデータの新しい利活用について取り上げてきた。連載で指摘が多かった,パーソナルデータの収集機会の増加,パーソナルデータの利活用の幅の増加を受けてガバナンスの重要性が高まっている。また,事業者は,個人情報保護法の改正動向にも着目しながら,積極的なパーソナルデータの利活用を検討すべきである。
Airbnbで学んだ「法務の時間術」6つの金貨
第3回 時間術は不幸せな仕事マシーンを量産するか
渡部友一郎
「時間を効率よく使えば幸せになれるのか?」
この問いは,忙しい現代を生きる法務パーソンにとって避けられないテーマです。書店に並ぶ時間術のテクニックを駆使して,タスクを片づけ,生産性を最大化しても,心の奥に空虚感が残るのなら,それは本当の成功とはいえないのではないでしょうか? 実際に,ギャラップ社の調査では,労働者の80%が「時間が足りない」と感じているそうです。
農林水産業法務を知る!
最終回 水産業
――資源の適切な保存・管理と漁業法
菅原清暁/西村 隆
将来にわたる持続的な水産資源の利用を確保するためには,水産資源の保存および管理を適切に行うことが必要であり,漁業においては,漁業法をはじめとして多くの法律によって規制が設けられている。多数存在する漁業関連の法律のうち中核をなすのは漁業法であり,漁業関連の事業を営むうえで,ぜひともその概要を押さえておくべきである。
テーマ別「インバウンド法務」の勘どころ
第2回 会社法,M&A
増山 健/大林良寛
本連載では,インバウンド法務を日々取り扱う弁護士らが,対談形式でテーマごとに案件の特徴や問題点等について語る。今回は,会社法,M&Aの分野について取り扱う。
野村修也
会社の経営者は,企業価値を向上させるにあたり,もっぱら株主利益の最大化を目指すべきなのか,それとも,他のステークホルダーの利益にも配慮すべきなのか。
ライアン・ゴールドスティン
交渉相手というと,とかく取引先等の社外の人を思い浮かべるかもしれない。しかし,部署内でも社内の他部署でも仕事においては交渉の連続である。「このプロジェクトをなんとか形にしたい」と,プロジェクトを軌道に乗せるために努力を重ねる読者や,自社におけるプレゼンスを「良い働き手」として上司や同僚に認識してほしいと願う読者もこのコラムを読んでくださっているだろう。
今回は日常のふとしたコミュニケーションのシーンを例にとり,自社におけるプレゼンスの高め方を検討してみよう。すでに取り組んでいる方も多いかもしれないが,自己点検のつもりでご一読いただきたい。
デジタルマーケティングの法律相談
第3回 個人情報保護法②
――委託に基づく利用範囲の限界と個人関連情報の利用
寺門峻佑/林 知宏/榊原颯子/牧 昂平
本稿では,委託提供の範囲外であると考えられているデータ活用施策および個人情報を活用したデータスキームを解説する。
悔しさを糧に――学べば開ける☆
第16話 大学卒業後は2年連続で総合Aの司法試験不合格に......。
木山泰嗣
弁護士としての実働から通算して20年を超えた税法学者が,税務の仕事に限らず,学生・受験生のころに経験したエピソードを挙げ,自分の思うようにいかない現状(=悔しさ)を糧に,どのように学び,どんな活路を開いてきたのかを語ります。
当局のプラクティスから学ぶ米国法
第2回 捜査への協力とは何か?
――他社が協力する際の対応
櫻林 賢/ヘザー・ランバーグ/李 明媛
米国司法省(以下「DOJ」という)の刑事捜査に協力をする旨のプレスリリースが会社から発表されることがあるが,そのようなプレスリリースを読んだ競合他社は,注意を払う必要がある。その協力活動によって,DOJが現在の捜査範囲を拡大し,まだ捜査対象となっていない他社と社員を捜査対象とすることがありうるからである。そのような会社は,捜査に協力する過程にどのような活動があって,DOJがどのようにその協力活動を用いて捜査を進め,または,拡大させるのかを理解することによって,迅速にリスクを見極めることができ,DOJからの捜査を待たずに,積極的に会社および社員を守るための戦略を講じることが可能となる。
PICK UP 法律実務書
『ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応』
北村喜宣
企業にあって環境法とのおつきあいを強いられている担当者が何より求めるのは,目の前にある問題にどのように対応すればよいかに関する即戦力の情報である。この期待にまったく応えないのが,研究者が執筆する環境法の体系書である。
海外法務書籍TREND
『International Space Law and Space Laws of the United States』
大久保 涼
この本は,ジョージタウン大学の宇宙法准教授かつNASAのインハウス弁護士として20年超の経験があるMirmina氏と,同大学の宇宙法准教授かつSpaceXやRelativity Spaceといった米国の宇宙スタートアップや政府機関で宇宙法をプラクティスしてきたSchenewerk氏によって執筆された。宇宙法を扱う法律家の多くは国際法の学者であるため,宇宙法の解説は非常にアカデミックかつ抽象的になり,実際に宇宙ビジネスをサポートしている実務家にとっては難解にすぎることがあるが,本書の筆者は肩書きからもわかるように,NASAや宇宙スタートアップ企業で日々宇宙法に関する実務的な課題と向き合ってきた実務家であるため,その説明は非常に明快かつ端的でわかりやすい。
「eスポーツビジネス」法的論点と対応
第4回 大会開催に向けたスポンサー契約
小石川 哲/加藤滉樹
本稿は,第3回と同様に,原則としてeスポーツ大会(以下「大会」という)の開催に向けた場面を想定する。主にスポンサーとして携わる企業の視点をふまえ,考えられる論点を整理し,スポンサーになる意義等を検討したうえで,スポンサー契約1において重要となる条項について解説を加える。
マンガで事例紹介!
フリーランスにまつわる法律トラブル
第10話 フリーランス特有の契約書
チェックポイント②
宇根駿人/田島佑規/ CS合同会社
今回は,前回の記事で少し取り上げた「取引を制限するような条項」について,より深掘りして解説していきます。