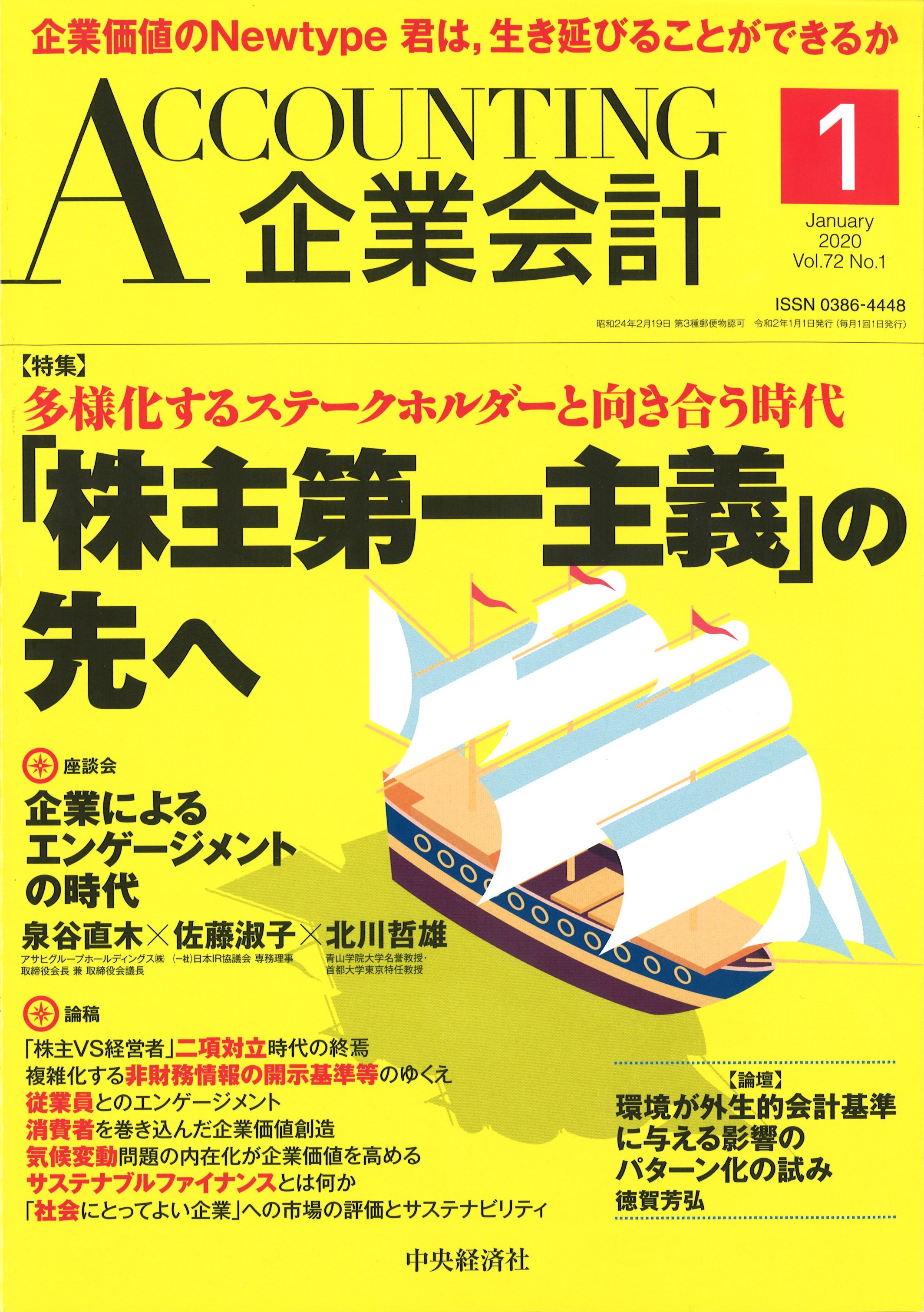  |
  |
査読付き論文コーナー創設にあたって
―ACC Peer-Reviewed―
近年,インターネットの普及により,内外問わず会計に関する様々な情報に容易に触れることができるようになり,雑誌媒体にはそれらの情報とは差異化された付加価値のより高い情報が求められています。小誌では,その情報ニーズに応えるために新たな試みを模索し,この度そうした試みの1つとして,これまで以上に信頼性の高い研究の成果を読者の皆さまに提供するため,「査読付き論文コーナー」を設けることといたしました。
(※)この査読付き論文については,通常の論文その他特集等の記事と区別し,掲載いたします。
「査読付き論文コーナー」編集委員会を代表して 編集長 斎藤静樹(東京大学名誉教授)
このコーナーは,会計の機能や制度に関する基礎的な研究成果の発信を目的に査読付きの論文を掲載します。編集にあたっては,①学術誌としての性格を堅持すること,②基礎的な研究を重視すること,③海外の研究動向に留意しつつ,日本語での発信に期待される役割を考慮すること,を基本原則とします。会計の基礎研究にとって重要な課題でありながら,海外で情報発信の機会が限られているものを含めて,この趣旨に沿った投稿を歓迎します。
(※)制度や実務の解説や提言を中心とする論文は対象ではありません。
投稿方法
投稿要項,執筆要項をご確認のうえ,専用ウェブサイトの投稿フォーム,またはメール(acc-pr@chuokeizai.co.jp)にて投稿してください。詳細は専用ウェブサイトをご確認ください。
| 答えて会計手帳が当たる! 年末恒例アンケート → 回答はこちらから | ||
| Scope Eye | ||
| 企業開示行政をめぐる最近の動向 | 金融庁企画市場局 企業開示課長 井上俊剛 |
|
| 会計時評 | ||
| 監査上の主要な検討事項の開示による経済的影響と課題 | 佐久間義浩 | |
| Salon de Critique | ||
| IASBの正統性はどこから生じるか | 森 洵太 | |
| 論壇 | ||
| 環境が外生的会計基準に与える影響のパターン化の試み | 徳賀芳弘 | |
| 特集 「株主第一主義」の先へ 多様化するステークホルダーと向き合う時代 |
||
| 座談会 企業によるエンゲージメントの時代 ――投資家との価値共創 |
泉谷直木 佐藤淑子 北川哲雄 |
|
| 「株主VS経営者」二項対立時代の終焉 ――サステナビリティ経営の情報開示 |
北川哲雄 | |
| 複雑化する非財務情報の開示基準等のゆくえ | 林 寿和 | |
| イギリス企業のCGコード対応にみる 従業員とのエンゲージメント |
林 順一 | |
| ファッション業界の最先端事例に学ぶ 消費者を巻き込んだ企業価値創造 |
青沼 愛 小崎亜依子 |
|
| 気候変動問題の内在化が企業価値を高める | 高村ゆかり | |
| 「リスク」「リターン」に続く評価軸「インパクト」 サステナブルファイナンスとは何か |
加藤 晃 | |
| 「社会にとってよい企業」への市場の評価とサステナビリティ | 大鹿智基 阪 智香 地道正行 |
|
| 第1回『企業会計』カンファレンス開催のお知らせ/査読付き論文コーナー創設のお知らせ | ||
| Accounting News | ||
| 金融庁解説 | ||
| 監査基準・中間監査基準・四半期レビュー基準の改訂について | 神保勇一郎 伊神智江 山崎優子 菅野直人 |
|
| 特別企画 ASBJでも検討スタート! LIBOR改革が会計に与える影響 |
||
| LIBOR改革と金融規制 | 岡本 修 | |
| IASBとFASBの動向 | 渡邊悦也 | |
| 新連載 | ||
| 税務と会計の水面下の戦い 昭和27年「税法と企業会計原則との調整に関する意見書」の効果 |
矢内一好 | |
| 事例でわかる 収益認識会計基準等の代替的な取扱い 代替的な取扱いの概要と契約変更の重要性が乏しい場合の取扱い |
市原順二 村山 華 |
|
| 連載 | ||
| 「おカネ」はどこから来て,どこへ行くのか リブラなんか恐くない |
福井義高 | |
| 会計「諺」則 会計奉公 |
片倉正美 | |
| 解題深書 日本企業復活のための政策と戦略 ――ガバナンス改革,働き方改革,そしてダイナミック・ケイパビリティ論 |
菊澤研宗 | |
| 日本企業における管理会計の実態調査 調査概要と原価計算編(東証・名証1部以外の上場企業) |
吉田栄介 岩澤佳太 |
|
| 主要論点をピックアップ 収益認識のポジション・ペーパー記載術 ライセンスの供与と基本論点 |
高田康行 | |
| 書評 | ||
| 林隆敏編著(日本公認会計士協会近畿会 監査会計委員会編集協力)『監査報告の変革』 | 朴 大栄 | |
| あずさ監査法人アカウンティング・アドバイザリー・サービス事業部編『経理・財務担当者のための「経営資料」作成の全技術』 | 小堺健司 | |
| 矢内一好『日本・税務会計形成史』 | 上野清貴 | |
| 学会ルポ | ||
| 日本会計教育学会第11回全国大会 | 金子友裕 | |
| 総目次 | ||
|
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集室より |
| △2019年8月,米国主要企業の経営者団体であるBusiness Roundtableは,企業の目的は“An Economy That Serves
All Americans”を促すことだと再定義する声明を公表し,日本では株主第一主義からの転換だと報じられました。日本がこれまで経営の見本の1つとみてきた米国の針路変更により,日本企業も,今後は新たなビジネスの大海原へと漕ぎ出していかなければいけないことを意味しています。では,その新たなビジネスの大海原とは一体どのような世界なのか? 本号特集(23頁以下)では現在起こりつつある変化の潮流を解説しています。 △本号特集で触れられている「すべて」のステークホルダーに配慮するということは,言うのは簡単です。しかし,現実問題として世界には様々な考えを持つ人が存在し,さらに利害まで対立しうるとなると,実践することは一筋縄ではいきません。その難しい方向へ世界が舵を取りつつあるなかで,企業が生き延びるカギの1つは,一貫した信念をもち,時には対立しつつも,あらゆるステークホルダーを自社のビジネスに巻き込みながら進むことのように思います。そうすれば,霧がかかって先の見えない状況のなかでも,難破することはきっとないはず。 △新年号では,普段立ち止まってなかなか考えられない,少し先の未来をイメージしていただくテーマを特集で取り上げましたが,多くの読者にとっては,最新のトピックも追いかけながら目の前の実務にいかに対応していくかが喫緊の課題だと思われます。特別企画(96頁以下)では,ASBJでも議論が始まったLIBOR改革について,そもそもLIBORとは何かといった基本的なポイントから,IASBとFASBの最新動向まで解説しています。ぜひご一読ください。 |
| 『企業会計』2020年2月号のご案内 |
|