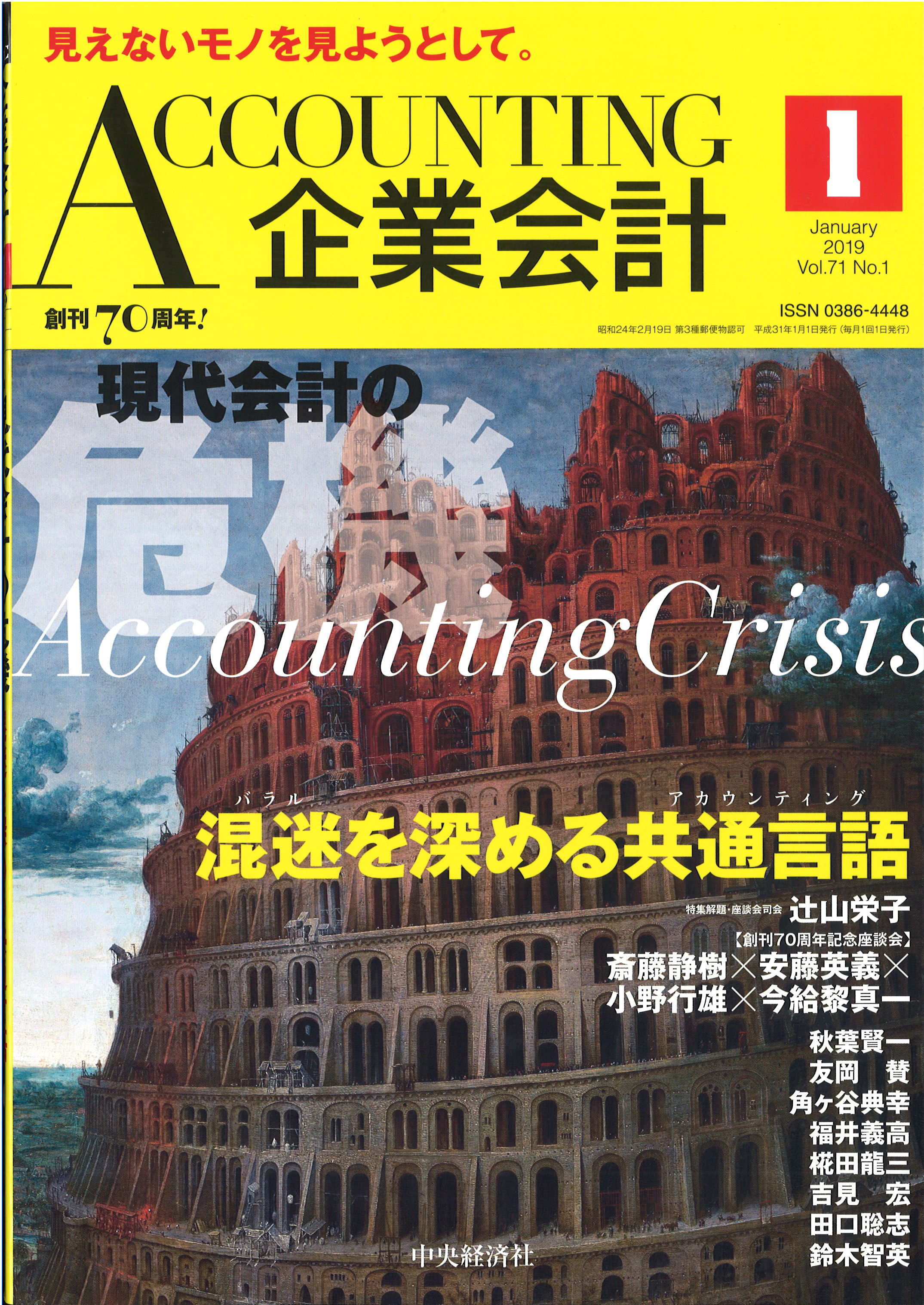  |
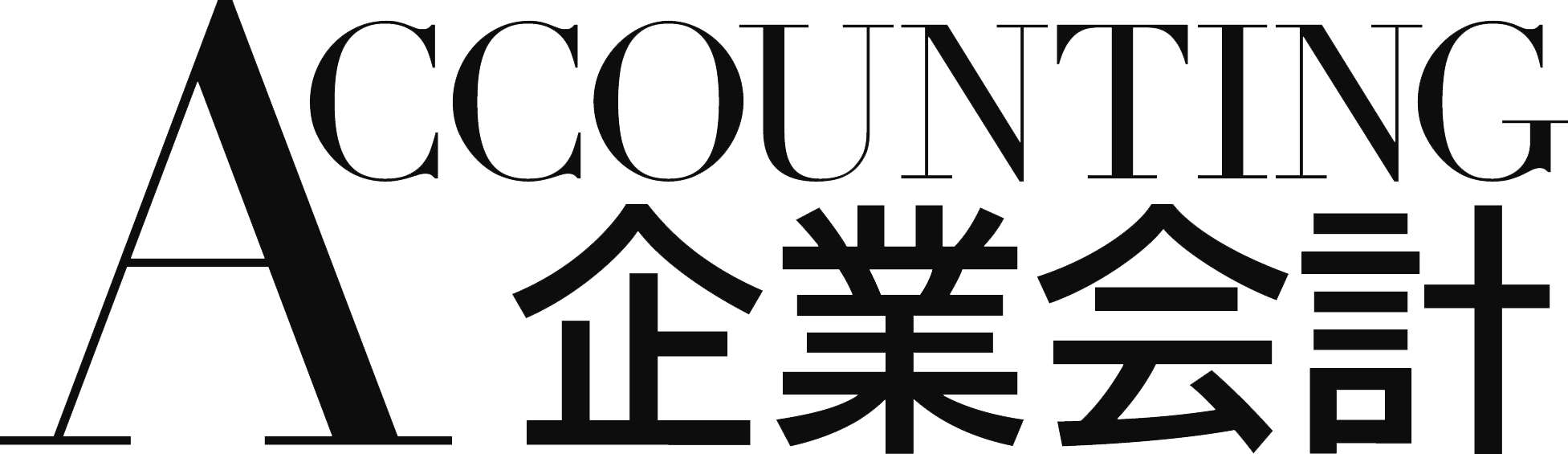  |
査読付き論文コーナー創設にあたって
―ACC Peer-Reviewed―
近年,インターネットの普及により,内外問わず会計に関する様々な情報に容易に触れることができるようになり,雑誌媒体にはそれらの情報とは差異化された付加価値のより高い情報が求められています。小誌では,その情報ニーズに応えるために新たな試みを模索し,この度そうした試みの1つとして,これまで以上に信頼性の高い研究の成果を読者の皆さまに提供するため,「査読付き論文コーナー」を設けることといたしました。
(※)この査読付き論文については,通常の論文その他特集等の記事と区別し,掲載いたします。
「査読付き論文コーナー」編集委員会を代表して 編集長 斎藤静樹(東京大学名誉教授)
このコーナーは,会計の機能や制度に関する基礎的な研究成果の発信を目的に査読付きの論文を掲載します。編集にあたっては,①学術誌としての性格を堅持すること,②基礎的な研究を重視すること,③海外の研究動向に留意しつつ,日本語での発信に期待される役割を考慮すること,を基本原則とします。会計の基礎研究にとって重要な課題でありながら,海外で情報発信の機会が限られているものを含めて,この趣旨に沿った投稿を歓迎します。
(※)制度や実務の解説や提言を中心とする論文は対象ではありません。
投稿方法
投稿要項,執筆要項をご確認のうえ,専用ウェブサイトの投稿フォーム,またはメール(acc-pr@chuokeizai.co.jp)にて投稿してください。詳細は専用ウェブサイトをご確認ください。
| Scope Eye | |||
| 企業開示行政をめぐる最近の動向 | 金融庁企画市場局企業開示課長 井上俊剛 |
||
| 会計時評 | |||
| 失敗の捉え方とチェックシステム ――人間観を通して |
栗濱竜一郎 | ||
| Salon de Critique | |||
| 会計は何かを遂行するのか? | 岡本紀明 | ||
| 特集 現代会計の危機 |
|||
| 特集解題「現代会計の危機」 | 辻山栄子 | ||
| 創刊70周年記念座談会 平成『後』の会計基準へ―Accounting in Post HEISEI |
斎藤静樹 安藤英義 小野行雄 今給黎真一 辻山栄子(司会) |
||
| Articles | |||
| 非上場株式の公正価値測定: 負の連鎖のはじまり |
秋葉賢一 | ||
| 会計と会計学のレーゾン・デートル | 友岡 賛 | ||
| 歴史的原価会計は危機に瀕しているのか | 角ヶ谷典幸 | ||
| 無益で不確かな割引現在価値情報 | 福井義高 | ||
| 受託責任概念と会計責任概念の後退 | 椛田龍三 | ||
| 会計専門職とその監査が直面する危機: 公認会計士に求められる判断 |
吉見 宏 | ||
| AI時代の会計の質の変容と「フューチャー・ハザード」 | 田口聡志 | ||
| 『会計と幸福』: 準需要飽和・準完全競争下の<経済>社会のアカウンティング |
鈴木智英 | ||
| 査読付き論文コーナー創設のお知らせ | |||
| Accounting News | |||
| 論文 | |||
| 日本電産の企業変革とCFO機能の役割 | 吉松加雄 | ||
| 連載 | |||
| Accounting Great Books 2nd ストーバス『投資者のための会計理論』 |
阿部光成 | ||
| DCF法実務の問題点:歪められた企業価値評価 DDM法の選択と検証 |
岩田悦之 | ||
| 書評 | |||
| 門田安弘『Economics of Incentives for Inter-Firm Innovation』 | 李 健泳 | ||
| 石光裕『研究開発費情報と投資家行動』 | 佐々木隆志 | ||
| 相談室Q&A | |||
| 〔法人税務〕2020年度から始まる 電子申告義務化への対応 | 佐久間裕幸 | ||
| 〔会社法務〕2020年から全面施行! 企業に求められる受動喫煙防止対策 | 横田真一朗 | ||
| 学会ルポ | |||
| 日本経営分析学会・日本ディスクロージャー研究学会連合大会2018 | 向 伊知郎 | ||
|
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お詫びと訂正本号「私の学問遍歴」にて,著者の西村明先生のお肩書に誤りがございました。西村先生をはじめ関係者各位に謹んでお詫び申し上げます。(編集部)(正)九州大学名誉教授・別府大学客員教授 (誤)九州大学名誉教授・大分大学客員教授 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集室より |
| △かつて人々は「同じ言語を持ち,同じ言葉を話していた」。そして,「一つの町を建て,その頂きが天に達する一つの塔を造」ろうとした。それをみた神は人々の言葉を混乱させ,人々を各地に散らすことによって,町の建設を放棄させた。そして「その町の名を乱れ(バベル)と呼ぶ」(以上,関根正雄訳『旧約聖書 創世記』(岩波文庫))。会計がビジネスの共通言語であることに疑いはありません。しかしモノの価値を,さらにはヒトの価値までも,すべて測ることができると考えるのは傲慢かもしれません。見えないモノを見ようとして,見えているモノを見落として,現代会計の危機が現出しているように思います。 △本号から新コラム「『論語と算盤』に学ぶ会計人の心得」(杉山稿118頁以下)が始まりました。日本資本主義の父として知られ,晩年には慈善事業にも携わるなど幅広く活躍した渋沢栄一。ご存じの方も多いとは思いますが,「倫理と利益の両立」を説いた渋沢の強い信念が,この『論語と算盤』に色濃く表れています。このコラムでは,現代のビジネスパーソンに必須ともいえる渋沢会計学の真髄を繙きます。熟読している人も書名しか聞いたことのないような人もぜひご一読ください。 △10月の終わりに開催された東京大学のホームカミングデイに足を運びました。お目当ては,国内大学初の試みである統合報告書の作成を紹介するイベントです。本誌2018年11月号の《会計「諺」則》をご執筆いただいたオムロンの安藤聡氏の講演をしっかりチェック。自社にとって何が重要なのか(materiality),その重みづけからしっかりと事業の優先順位(priority)を考えないといけないという話が印象的でした。読者の皆さまにとって本誌購読の優先順位があがるよう,本年もがんばります。 |
| 『企業会計』2019年2月号のご案内 |
|
||||||||||||||||