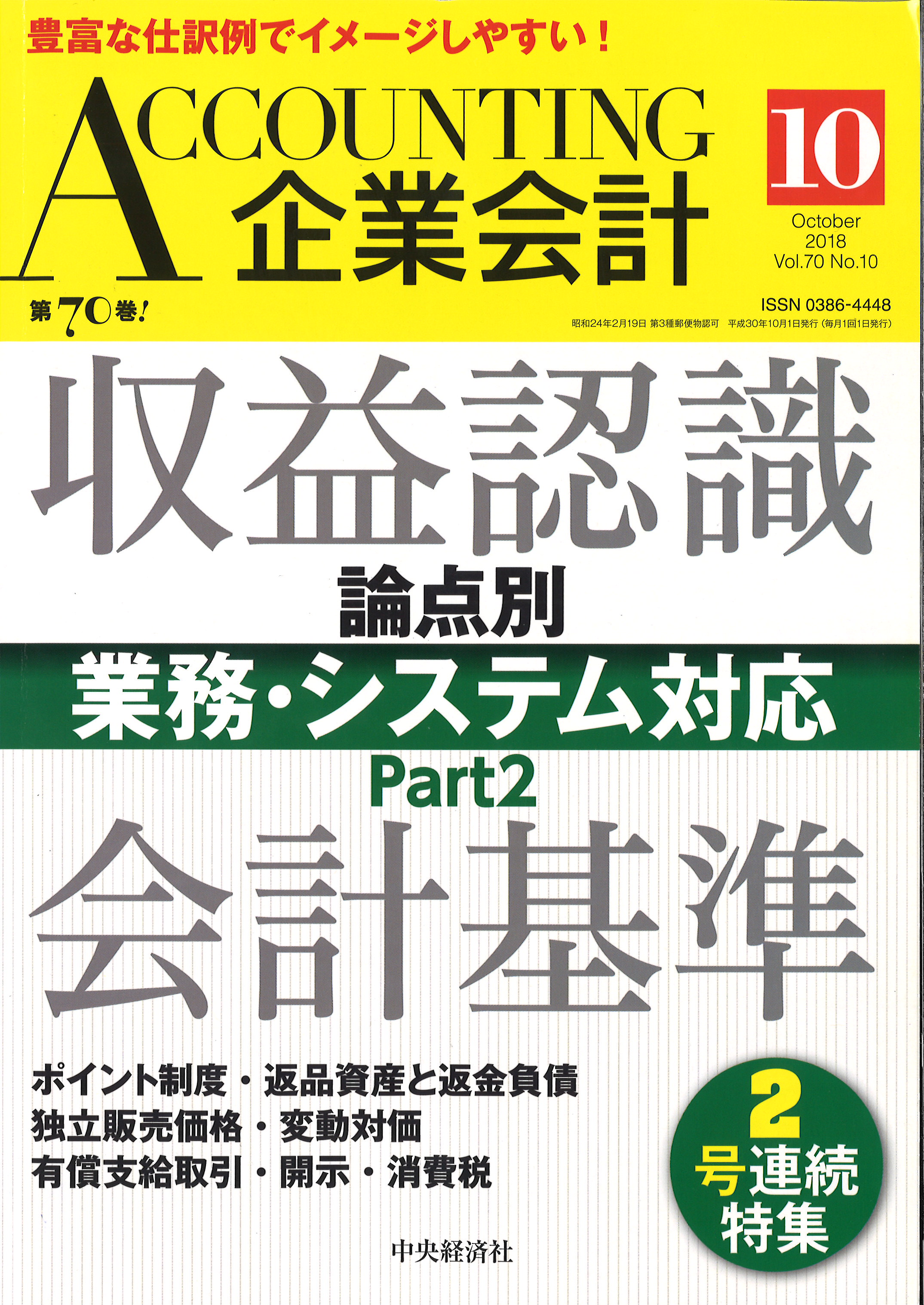 
|
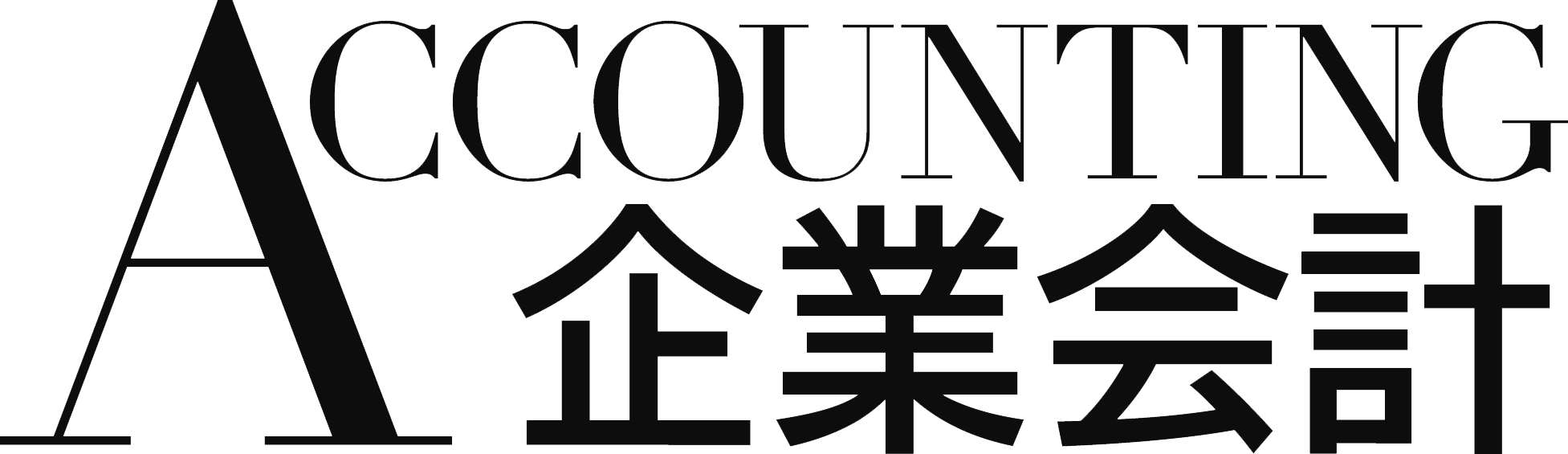 |
査読付き論文コーナー創設のお知らせ
―ACC Peer-Reviewed―
近年,インターネットの普及により,内外問わず会計に関する様々な情報に容易に触れることができるようになり,雑誌媒体にはそれらの情報とは差異化された付加価値のより高い情報が求められています。小誌では,その情報ニーズに応えるために新たな試みを模索し,この度そうした試みの1つとして,これまで以上に信頼性の高い研究の成果を読者の皆さまに提供するため,「査読付き論文コーナー」を設けることといたしました。
(※)この査読付き論文については,通常の論文その他特集等の記事と区別し,掲載いたします。
「査読付き論文コーナー」編集委員会を代表して 編集長 斎藤静樹(東京大学名誉教授)
このコーナーは,会計の機能や制度に関する基礎的な研究成果の発信を目的に査読付きの論文を掲載します。編集にあたっては,①学術誌としての性格を堅持すること,②基礎的な研究を重視すること,③海外の研究動向に留意しつつ,日本語での発信に期待される役割を考慮すること,を基本原則とします。会計の基礎研究にとって重要な課題でありながら,海外で情報発信の機会が限られているものを含めて,この趣旨に沿った投稿を歓迎します。
投稿方法
以下より投稿要項,執筆要項を確認のうえ,メールにてacc-pr@chuokeizai.co.jpまで投稿してください。
| Scope Eye | ||
| 日本企業のIRの進化 | 東京海上ホールディングス㈱取締役会長 隅 修三 |
|
| 会計時評 | ||
| 会計における「想像力」 | 高橋 賢 | |
| Salon de Critique | ||
| クロスボーダーM&Aの成否を問う | 宮宇地俊岳 | |
| 特集 収益認識会計基準 論点別 業務・システム対応 Part2 |
||
| 特集解題:業務・システム対応の4つのステップ | 山本浩二 | |
| ポイント制度の課題対応 | 山本浩二 | |
| 返品資産と返金負債の管理 | 那須 玄 | |
| 「独立販売価格」への対応 | 山本浩二 | |
| 「変動対価」への対応 | 山本浩二 | |
| 有償支給取引の実務対応 | 中原康宏 河上修一郎 |
|
| 開示の実務 | 前田和哉 | |
| 消費税:第三者のために回収する額 | 荒井優美子 | |
| 査読付き論文コーナー創設のお知らせ | ||
| Accounting News | ||
| 時事解説 | ||
| 社外取締役の「独立性」を投資家はどうみるか | 藏本祐嗣 | |
| シェアリングエコノミーは「会計」を変えるか | 榊 正壽 | |
| アメリカのM&A訴訟にみる「公正な価格」決定の争点 | 吉村一男 | |
| 連載 | ||
| 会計「諺」則 練習は不可能を可能にする |
柳澤義一 | |
| バーゼルⅢの最終化がもたらす金融商品会計への影響 終・デリバティブ規制とデリバティブ投資 |
岡本 修 | |
| Accounting Great Books 2nd ケアリー『公認会計士:業務の未来設計』 |
阿部光成 | |
| 「監査上の主要な検討事項」 ――欧州企業の記載事例分析 のれん |
富田真史 猪原匡史 |
|
| DCF法実務の問題点:歪められた企業価値評価 予測キャッシュフローの合理性の検証(2) |
岩田悦之 | |
| 解題深書 消費税10%に備えよう! |
中島礼子 | |
| 相談室Q&A | ||
| 〔法人税務〕クラウドサービス導入時の電子帳簿保存法対応 | 山口隆司 | |
| 〔会社法務〕ビッグデータ解析への影響は? 改正不正競争防止法の留意点 | 渡邉 峻 | |
| 書評 | ||
| 企業予算制度研究会編『日本企業の予算管理の実態』 | 小菅正伸 | |
| 石川純治『基礎学問としての会計学』 | 辻山栄子 | |
| 中村亮介・河内山拓磨『財務制限条項の実態・影響・役割』 | 首藤昭信 | |
|
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集室より |
| ◇8月号からお知らせしている《査読付き論文コーナー》の募集がいよいよこの9月からスタートします(本号8頁参照)。目下,論文の投稿やダウンロードのプラットフォームとなる専用ウェブサイトを製作中ですが,それまでは弊誌ウェブサイト(https://www.chuokeizai.co.jp/acc)にて,投稿要項,執筆要項などを公開しています。専用ウェブサイトでは,当該コーナーに関する様々な情報を充実させていく予定ですので,いましばらくお待ちください。何より,皆さまのご投稿をお待ちしております。 ◇やっぱり簿記は奥深い! 特集で取り上げた“有償支給時の仕訳”。編集部の書棚から定本をひっぱり出してみてみると,借方に未収入金〈売掛金〉,貸方には支給品〈材料〉(岡本清『原価計算(六訂版)』150頁)。ところが,公開草案の設例は,この取引を融資のように見立て,借方に未収入金,貸方に有償支給取引に係る負債をたてる。最終化された適用指針には,有償支給取引の設例がありません。実務上は悩ましいことこのうえありませんが,簿記研究の観点からは非常に興味深い論点が詰まっているのでは。 ◇会計と音楽は似ているところがある? 一見全く関係のなさそうな両者ですが,本号「会計時評」(高橋稿4頁以下)では,外部の記録(帳簿・楽譜)をもとに,読み手が想像力を働かせて解釈し,実際の取引・メロディーを再現できるという類似点を紹介しています。私も久しぶりに音楽でもやってみようかという気になって,ギターをひっぱり出して弾いてみたところ,指が動かない…。「想像力」を働かせるためには,日々のルーティンやそこで磨かれる技能が大切なんだと改めて感じた次第です。記録の改変が注目されがちだけど,単純な再現も大変なんだなあ。 |
| 『企業会計』2018年11月号のご案内 |
| 〈特集〉 監査役等と会計士のコミュニケーションが必須!! 「監査上の主要な検討事項」への対応 (タイトル・テーマは予告なく変更する可能性がございます。) |