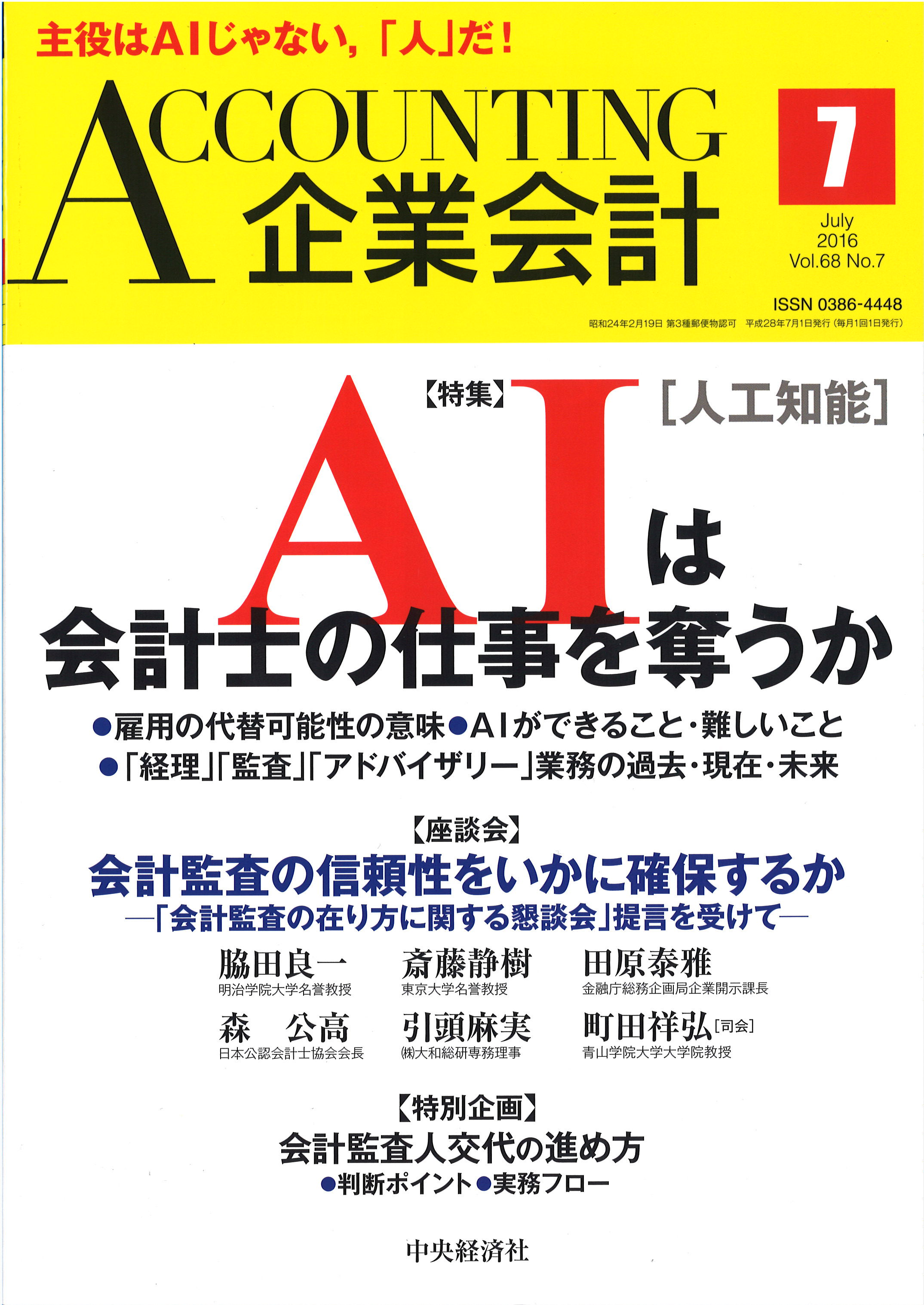 
|
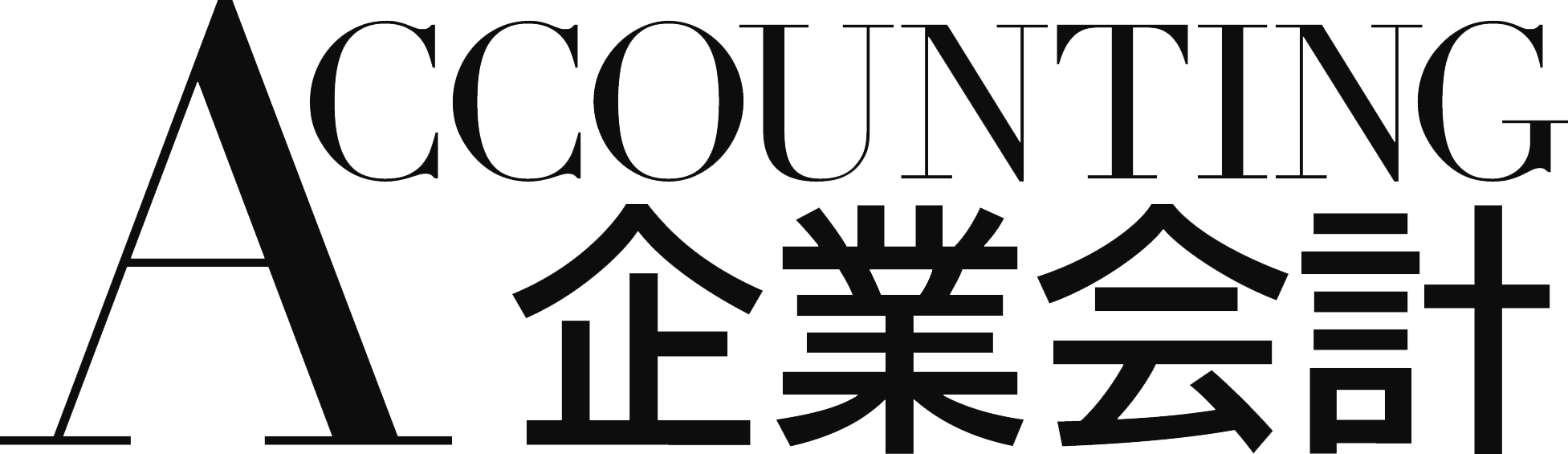 |
| Scope Eye | |
| 業績ではなく社員第一主義経営 | 法政大学大学院教授 坂本光司 |
| 会計時評 | |
| 会計専門家の判断特性の可視化 | 角ヶ谷典幸 |
| Salon de Critique | |
| 会計の社会学的分析とは(1) | 堀口真司 |
| Accounting News | |
| 特集 AIは会計士の仕事を奪うか | |
| AI・ロボットによる雇用の代替可能性の意味とは? | 上田恵陶奈 |
| AIができること・難しいこと | 山田誠二 |
| 経理業務:自動化を促す会計システムの進化 | 原 幹 |
| 監査業務:「試査」から再び「精査」の時代へ | 小川 勤 |
| アドバイザリー業務:仮想知的労働者が企業活動を変える | 田中淳一 |
| 座談会 会計監査の信頼性をいかに確保するか ――「会計監査の在り方に関する懇談会」提言を受けて |
|
| 脇田良一 斎藤静樹 田原泰雅 明治学院大学名誉教授 東京大学名誉教授 金融庁総務企画局企業開示課長 森 公高 引頭麻実 町田祥弘[司会] 日本公認会計士協会会長 ㈱大和総研専務理事 青山学院大学大学院教授 |
|
| 特別企画 会計監査人交代の進め方 | |
| 会計監査人交代の判断ポイント | 塚本英巨 |
| 会計監査人交代の実務フロー | 中村慎二 |
| 解題深書 | |
| 監査の現場を知る――公認会計士は何を考え,何をしているのか | 山田善隆 |
| 時事解説 | |
| 「IFRS第15号『顧客との契約から生じる収益』の明確化」のポイント | 川西安喜 |
| 実務のココが知りたい! IFRS第16号「リース」Q&A(下) |
植木 恵 |
| 連載 | |
| IFRS第0号「用語」 第4項 公正価値 |
伊藤清治 |
| 会計「諺」則 熱と誠 |
北村敬子 |
| 新連載 2015年調査から考える 為替リスク管理の効果的実践 第1回 なぜいま為替リスク管理か |
加賀谷哲之 小柳陽一朗 |
| じっくり語ろう監査のはなし 第3回 大手監査法人ならば品質は高いのですか?――監査人の規模の観点から |
町田祥弘 |
| 資本の兵法 第七篇 企業価値向上を目指した資本政策の実践 |
木下徳明 |
| 相談室 | |
| 〔法人税務〕国税関係書類のスマホ撮影保存 | 佐久間裕幸 |
| 書評 | |
| 金子康則〔編著〕 『金融機関のためのネッティングの実務』 | 秋葉賢一 |
| 金森絵里 『原子力発電と会計制度』 | 醍醐 聰 |
|
 |
| 編集室より |
| ▽今号の特集は「AIは会計士の仕事を奪うか」(15頁以下)。囲碁や将棋に象徴されるように,「人対AI」が強調されがちですが,AIは突如として立ちはだかった人類の敵ではありません。「世の中をもっとよくしたい」という人の気持ちから生まれてきました。会計士として働いている読者の皆さまもその思いは共通しているのでは。世の中思ったとおりにはなかなか進みませんが,思いがなければ始まらない。仕事を始めたころの初心に立ち返るきっかけにもなれば幸いです。 ▽オランダのマーストリヒトで開催されたヨーロッパ会計学会(EAA)に参加する機会を得ました。テロの記憶も覚めやらぬブリュッセルを経由したのですが,現地の方によるとベルギーにはブリュッセル,フランドル,ワロンと3つの異質な文化があるとのこと。異質な文化の共存を可能にするものこそ「寛容」だけれども,寛容すぎてテロが起きてしまったかもしれないとも。学会では,学問の厳しさはもちろん,EAAを特徴づける(?)寛容な雰囲気も味わうことができました。 ▽笑点の司会が交代しました。思わぬ人選!? との声もありますが,今までとは一味違う大喜利がとても楽しみです。同様に,と言ってはお叱りを受けそうですが,会計監査人の交代もなかなかお目にかかれないイベントです。しかし,監査法人のローテーション制度が改めて注目されるなか,「画一的な強制」(座談会71頁斎藤先生発言)に至る前に,企業が会計監査人をより積極的に選択すべき時が来たのかもしれません。今号特別企画(97頁以下)をもとに各社で議論してみてはいかがでしょうか。 |
| 企業会計2016年8月号のご案内 |
| 旧商法改正・事件史 コーポレートガバナンスの本質を辿る ■取締役会の誕生 ■監査役制度の変遷 ■会計監査人の導入 ■委員会設置会社:3つの委員会 ■委員会設置会社:執行役制度 ■内部統制の整備 ■ガバナンスと取締役の経営判断 ■ストック・オプション制度 ■利益供与(総会屋)と代表訴訟 〈論壇〉 中野常男 国士舘大学教授・神戸大学名誉教授 (タイトル・テーマは予告なく変更する可能性がございます。) |