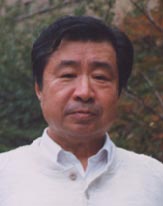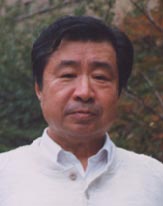|
福祉の研究の場へ
京都大学停年の年に日本福祉大学経済学部に経営開発学科が新設され,そこに移ることになった。1年後,大学付置の福祉社会開発研究所の所長を命ぜられ,今年で4年目を迎えた。福祉教育の草分け的歴史を持つ大学に赴任し,長寿社会を支える介護保険制度の導入を迎えたのである。この結果,私自身の研究も,福祉・医療経営での会計の役割に傾斜することになる。
少子高齢化社会を迎えて
福祉政策の焦点は,今日なんといっても高齢者福祉であろう。その結晶が介護保険制度といえよう。従来の措置費による福祉行政から,介護保険制度による福祉給付は,なにをもたらすことになるのか,会計の役割はどのように変化するのだろうか。さらにこれに加えて,営利企業の参入を認め,福祉市場に「自由化」競争が部分的にしろ導入された。クライアントには,サービス供給業者を「選択」することが出来るようになったのである。
措置費による福祉給付は,基本的に行政による裁量に依存するため,福祉施設側には経営責任の自覚は低かったといえよう。しかし,介護保険制度は要介護度の認定の違いにより,保険給付額が変動する。しかも,医療保険と違い,上限がある。このため,施設経営の自己責任は,経営的判断を不可欠のモノとすることになる。臨床ケアにのみ専念できた時代は終わり,経営としてのマネジメント能力が問われることになったのである。
また,サービス供給力の少ない地域では,地域格差の問題が浮上し,自治体の福祉行政の責任が問われることにもなる。要介護の出現率や月額保険料の算定,上乗せ・横だしサービスなど,行政の経営的センスとインフラストラクチャの整備の先見性などが,隣接する市町村と対比される時代に入ったのである。
福祉・医療の複合体経営の広がり
高齢者福祉(加齢による介護)は,高齢者医療と隣り合わせの関係にあるのが,臨床の現実である。高齢者は,ちょっとしたことで医師のケアを必要とすることがある。そのため,近くに,医師や看護婦が居てくれるだけで安心なのである。
医療法人は,福祉法人と違い,医療保険の点数制度によって経理面で鍛えられてきた。ベッド数,救急と慢性の疾病,検査・投薬など,善意の臨床ケアだけでは済まない経営サイドからの検討を強いられてきたのである。医療保険の制度改訂にも注意を払わなければならなかった。たとえば,薬価基準の改訂や医療費抑制政策の影響などである。
このような経験は,医療法人が,福祉法人に比べて,きわめて強い経営志向に染まる要因でもあった。だから,経営的に効果的なケアミックスを提起できる事務長クラスの人材が育ってきたのである。さらに,病院患者の半数以上が高齢者で占められるなかで,高齢者医療費の抑制策と高齢者福祉の将来計画に,強い関心を寄せたのは,医療法人であった。
こうした事態の推移のなかで,比較的中小規模の病院を中心に,福祉施設を別法人で開設し,理事長を同一人物が兼務する医療・福祉の複合体経営が増加してきたのである。両施設は,同一敷地内にあったり,廊下で結ばれていたり,同じ建物の中で,階が違うだけなど,いろいろな種類がある。この実態は,福祉大学の同僚である二木教授の研究に詳しくまとめられている(二木 立「保健・医療・福祉複合体」医学書院,1998)。なお,二木によれば,複合体の典型とされる「3点セット」は,私的病院・老人保健施設・特別養護老人ホームである。
福祉社会開発研究所の共同研究「複合体の日米比較」で,二木教授と今年1月にカリフォルニアの病院を訪問・調査してきた。ロスアンジェルスのカソリック病院の体験は印象的であった。NPO のこの病院は,スラム地域の医療福祉を自らのミッションとして掲げていた。ナース出身のCEO は,スラム対策に力を入れるためには,行政からの補助金は不足しているので,NPO の病院ではあるが,効率的運営により剰余を稼がなければならないと強調したのである。
福祉・医療複合体における会計の役割
日本の場合も含めて,高齢者福祉を担う複合体は,医療法人,福祉法人ごとの財務会計を持っている。さらに,両法人の連結データと将来の設備投資計画・スタッフの異動・増員を含む要員計画など管理会計手法を導入しつつある。しかも,業績評価は,営利企業の利益単一指標から,多元的評価基準に拡大されている。出資者への利益配当は課題でないため,剰余は設備投資や研修などへ再投資され,各法人ごとの採算はキャッシュフローベースでチェック,複合体としての資金運用が検討されるところまできているのが先進的な実例である。
医療法人の理事長は医師でなければならないが,すでに,医師自身が,経営学や会計学の勉強を始めている例は少なくない。理事長として,臨床から管理業務に転身したドクターも多い。また,各法人ごとに人事・経理などを統括する事務長の存在は,どこでも見られるが,複数の法人を統括する事務局長をもつ複合体も存在するのである。
多くは,先見性のある医療法人に見られることではあるが,成り行き管理のレベルにある福祉施設と比べると,病院主導の複合体経営は,財務会計のみならず,管理会計手法を連結データのもとで展開する水準に達している。そのために,これらの複合体は,臨床ケアの分野のほか,財務・会計分野でもヘッドハンティングを実施してきたのである。
数少ない先駆的事例とはいえ,非営利の福祉・医療複合体経営が,ここまで会計の役割を使いこなす段階に達していることは,驚きでもあった。
|